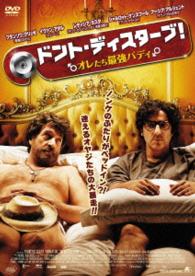内容説明
戦争全体の把握にはデータが肝要だ。特に死者数のデータは、戦争の規模、相手との優劣比較で最も説得力を持つ。ただ発表されるデータが正しいのかは常に疑念があるだろう。ウクライナ戦争での戦死者数についても、ウクライナ、ロシア双方から発表される数字は異なる。では、そうしたデータはどのように集められてきたのか。
戦場での死者数は、総力戦となった第1次世界大戦以降、国家による将兵だけの把握では難しくなり、赤十字国際委員会、国際連盟といった国際機関が介在していく。しかし第2次世界大戦後、特定地域での内戦・紛争・ゲリラ戦が頻発。政府側・反政府側で異なる数字が発表されていく。大国間対立で国連が機能不全に陥るなか、国際的な人道ネットワークが、先進各国や国連の支持を受け、死者数の調査・精査を行い発表していく。
本書では、特に1960年代以降のベトナム戦争、ビアフラ内戦、エルサルバドル内戦から、第3次中東戦争、イラン・イラク戦争、旧ユーゴ紛争、そして21世紀のシリア内戦、ウクライナ戦争を辿る。その過程で国際的な人道ネットワークが、統計学や法医学の知見を取り入れ、どのように戦争データを算出するようになったか、特に民間人死者数に注目する。また、データをめぐる人々の苦闘にも光を当てる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
135
報道で「ウクライナ侵攻で死者が50万人」とある。さて、死者数は誰がどうやって数えるか、戦闘員と文民の内訳は?、戦場で遺体はどう処理されるかなどという疑問に向き合ったユニークな一冊である。戦争統計データの取り方、文民保護の考え方(文民の定義は?)などの国際的なルール作りの歴史がよくわかる。国民国家が信用できない中で、NGOが重要な機能を果たしていることも理解できた。でも、どんなに統計手法を厳密にしたところで、一人の貴重な人生を「死者1名」というデータとして扱う不条理に対する空しさは、戦争も震災も一緒である。2024/02/01
どら猫さとっち
13
戦争で亡くなられた方たちは、どのように統計するのか。困難なデータ方法は、どのようにしているのか。本書はそれを詳しく説明している。とはいえ、死者数の数値には、どのような思いで戦場に赴き死んでいったか。また行方不明者もいることもあり、数値化の裏にある生命の尊さも浮かび上がる。データの誤魔化しや改竄はあってはならないが、統計することの難しさに思い悩ます。それは震災でも同じことが言える。2024/03/05
かんがく
11
今まであまり触れてこなかったアプローチで戦争について学べた。統計という科学が常に受け容れられるわけではない。2025/09/18
おやぶたんぐ
10
戦争による人間の死が単なる数字に換算されてしまう恐ろしさ、と言われるが、数字に換算すらされない恐ろしさには到底及ばない。そして、数字に換算する困難さ、換算された死の意味を認識する困難さも案外軽視されているようにも思われる。本書はこの恐ろしさ、困難さの一端を見せてくれる。少なくとも、党派性で全てを論じ、分かったような気になるのが誤りであることだけは間違いないだろう。2024/02/11
_apojun_
8
図書館本。 ちょっとタイトルを深読みしすぎて思っていたのと違う内容で敷いたが、とてもためになりました。 戦争の報道等で知らされる「戦死者の数」というものが、どういう風にカウントされているのか、その過程を詳しく説明されています。 確かに「戦死者数」というのは良く耳にしますが、だれがどうやって数えているんだろう、なんてこれまで気に留めたこともなかったな。 後、データについては「科学的耐久性」が大切と説かれているけど、科学的耐久性の高いデータが必ずしも社会的に受け入れられるわけではないと、なるほど。2025/10/07
-
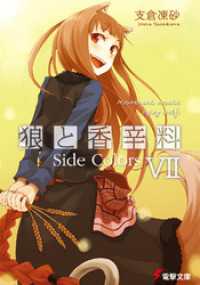
- 電子書籍
- 狼と香辛料VII Side Color…