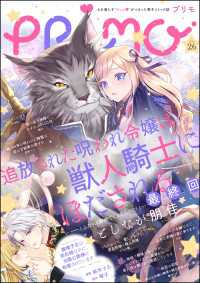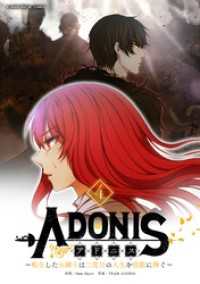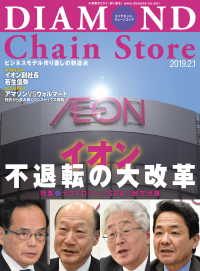内容説明
日本の神々とは日本人にとってどのような存在だったのか。神々は日本の風土のなかでどのような役割を担っているのか。日本の神は、自然を畏敬し国土の安寧を願う出雲系と、天皇による国家支配を正当化する高千穂・日向系に分かれる。高千穂・日向・出雲で景観問題の解決に奔走した著者が神話の舞台を歩き、「古事記」「日本書紀」編纂の場である飛鳥の遺跡に身を置いて、神々の来歴にひそむ謎を解く。【目次】序章 女神はなぜ洞窟に隠れたか――高千穂神話の世界から/第I部 出雲の神々の世界へ/第一章 スサノオの国づくりと和歌の起源――出雲平野の「わが心すがすがし」/第二章 斐伊川水系大治水計画――昭和・平成のオロチ退治/第三章 天下経営の大神――出雲大社表参道神門通りの道づくり/第四章 水に臨む神々――城原川流域委員会/第五章 疫病神の活躍――鞆の浦まちづくり/第II部 風土に生きる神々/第六章 巨大ナマズと戦う神々――要石とプレートテクトニクス/第七章 「ふるさと見分け」の方法――姥ヶ懐・裂田溝の危機/第八章 白き山の姫神――在地神と外来神/第九章 座問答――古代の大合併と合意形成の知恵/第十章 神々誕生の海岸――宮崎海岸侵食対策事業/第III部 神話から歴史への旅/第十一章 飛鳥にて――『古事記』『日本書紀』編纂スタートの地/第十二章 神話と歴史をめぐる三つの疑問/第十三章 飛鳥浄御原宮――神話と歴史を編む/第十四章 前例としての日本神話/第十五章 古代からの伝言――危機の時代のリスクマネジメント
目次
まえがき/序章 女神はなぜ洞窟に隠れたか──高千穂神話の世界から/神代川のほとりに立つ/「神代川かわまちづくり計画」/神代川河川整備起工式祝詞/高千穂神楽/姉神と弟神はどうして対立したか/第I部 出雲の神々の世界へ/第一章 スサノオの国づくりと和歌の起源──出雲平野の「我が心すがすがし」/荒神谷遺跡/古代斐伊川の風景と和歌の起源/出雲神楽/天叢雲剣/第二章 斐伊川水系大治水計画──昭和・平成のオロチ退治/世紀の大治水事業と紛争解決の仕事/神々の風土を旅する/「大橋川周辺まちづくり基本方針」/第三章 天下経営の大神──出雲大社表参道神門通りの道づくり/「祈りの道、そして出会いの道」/オオクニヌシの名前/オオクニヌシとはどんな神か/第四章 水に臨む神々──城原川流域委員会/スサノオゆかりの湖・川・海/城原川流域委員会/景行天皇とその皇子、ヤマトタケルはスサノオを祀った/第五章 疫病神の活躍──鞆の浦まちづくり/鞆の浦の景観論争/蘇民将来伝説/牛頭天王と祇園祭/伊勢のスサノオ/第II部 風土に生きる神々/第六章 巨大ナマズと戦う神々──要石とプレートテクトニクス/鹿島神宮と香取神宮/要石/大ナマズとの戦い/科学と神話/鹿島・香取から春日へ/第七章 「ふるさと見分け」の方法──姥ヶ懐・裂田溝の危機/豊前の海の聖地・姥ヶ懐危うし/日本最古の農業用水路・裂田溝を守れ/第八章 白き山の姫神──在地神と外来神/白山比咩大神/多様な神々の来歴/神々の区分/第九章 座問答──古代の大合併と合意形成の知恵/相模国の国府祭と古代の中央集権化政策/相模国の六社/新緑のなかの座問答/第十章 神々誕生の海岸──宮崎海岸侵食対策事業/日向国の海岸の危機/つぎつぎに生まれ出る神々/高千穂神話から日向神話へ/神々の系譜から天皇の皇統へ/第Ⅲ部 神話から歴史への旅/第十一章 飛鳥にて──『古事記』『日本書紀』編纂スタートの地/大和川流域/曽我川/飛鳥豊浦宮/甘樫丘に立つ/第十二章 神話と歴史をめぐる三つの疑問/なぜ天皇は出雲神を祀ったか/なぜ天皇は祟られたか/なぜ暴虐な天皇が記録されたか/『古事記』と『日本書紀』/第十三章 飛鳥浄御原宮──神話と歴史を編む/女帝の時代/乙巳の変の現場に立つ/吉野の盟約と歴史編纂の詔勅/天武天皇から持統天皇へ/黒作懸佩刀/第十四章 前例としての日本神話/平城京の通勤路/高天原の誓約と「不改常典」/なぜ草薙剣は天武天皇に祟ったか/第十五章 古代からの伝言──危機の時代のリスクマネジメント/出雲の神々はなぜ生き残ったか/祟りのもつ意味/権力と権威の不即不離/危機にそなえて/あとがき/系図/年表/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
わ!
Junko Yamamoto