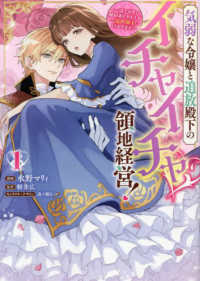内容説明
子どもの夜泣き、核家族の不幸、汚職や賄賂、陰謀論……
すべては進化のせいだ!
斯界の権威が大絶賛!
「洞察に満ちた科学的理論と興味深い逸話の詰まった快作」
――リチャード・ドーキンス(進化生物学者、『利己的な遺伝子』著者)
「協力がいかに大切かについて書かれた、素晴らしい本」
――アリス・ロバーツ(人類学者、『人類20万年 遙かなる旅路』著者)
「私たち人類についての考え方を変える」
――ルイス・ダートネル(宇宙生物学者、『この世界が消えたあとの 科学文明のつくりかた』著者)
「世界をよりよく理解する方法だけでなく、世界をどう変えるかについても示してみせる」
――マシュー・コブ(動物学者)
「人間がそうであるべきほど協力的でないのはなぜかを知りたければ、答えは本書の中にある」
――ロビン・ダンバー(進化生物学者、『友達の数は何人?』著者)
■本書で得られる知見
・多細胞生物が誕生したのは「協力」が利益をもたらすためである
・ミツバチやアリのコロニーは「超個体」のように振る舞う
・母親と胎児は栄養分をめぐって争う
・姑が嫁の子育てを手伝うのにはわけがある
・詐欺やたかり、汚職や賄賂、身内びいきも協力の産物である
・パラノイア(妄想症)や陰謀論の背後にある進化論的な理由
・平等主義だった人類の社会に独裁制が誕生したのはなぜか?
・集団の人数が増えると反乱は起きにくくなる
目次
はじめに
第1部 「自己」と「他者」ができるまで
第1章 協力を推し進めるもの
第2章 個体の出現
第3章 体のなかの裏切り者
第2部 家族のかたち
第4章 育児をするのは父親か母親か
第5章 働き者の親と怠け者の親
第6章 人類の家族のあり方
第7章 助け合い、教え合う動物たち
第8章 長生きの理由
第9章 家族内の争い
第3部 利他主義の謎
第10章 協力の社会的ジレンマ
第11章 罪と協力
第12章 見栄の張り合い
第13章 評判をめぐる綱渡り
第4部 協力に依存するサル
第14章 他人と比較することへの執着
第15章 連携と反乱
第16章 パラノイアと陰謀論
第17章 平等主義と独裁制
第18章 協力がもたらす代償
謝辞
参考文献と原注
用語一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おせきはん
りょうみや
Y田
naohumi
リットン
-

- 電子書籍
- ぷちはうんど(1) 月刊コミックブレイド
-

- DVD
- 花のお江戸の釣りバカ日誌