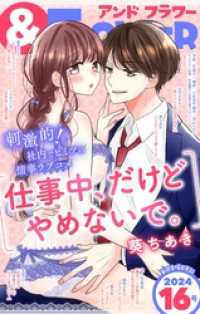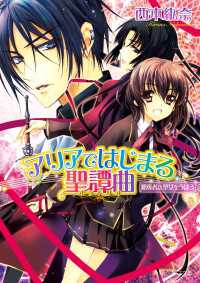- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
人間以外の生物は、老いずに死ぬ。
ヒトだけが獲得した「長い老後」には重要な意味があったーー。
生物学で捉えると、「老い」の常識が覆る!
【ベストセラー『生物はなぜ死ぬのか』著者による待望の最新作!】
・産卵直後に死ぬサケ、老いずに死ぬゾウ、死ぬまで子が産めるチンパンジー
・ヒトは人生の40%が「老後」
・長寿遺伝子の進化
・寿命延長に影響した「おばあちゃん仮説」と「おじいちゃん仮説」
・老化するヒトが選択されて生き延びた理由
・ミツバチとシロアリに学ぶ「シニアの役割」
・昆虫化するヒト
・不老長寿の最新科学
・85歳を超えたら到達できる「老年的超越」というご褒美
・老化はどうやって引き起こされるのか
・生物学者が提言する「最高の老後の迎え方」とは ……ほか
「老いの意味」を知ることは「生きる意味」を知ることだった。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
136
「生物はなぜ死ぬのか」に続く小林先生の著作。全ての生物に死があるのに、なぜ「老い」はヒトだけなのか。ヒトと近いゴリラやチンパンジーでも、閉経とともに寿命を迎え老後がないのに、なぜヒトは生殖可能期間を越えて40年も生きるのか。そんな疑問に対する基礎生物学の答えを知りたかった。DNAの損傷が幹細胞で起きて細胞の供給能力が低下しても、(細胞が更新されない)心臓と脳の機能が低下しても、個体の死に至らない老化の謎は、今一つ解消されない。本書の後半は、老人の処世訓のような話ばかりで、内容がタイトルから乖離してゆく。2023/08/10
tamami
84
著者は、前作『生物はなぜ死ぬのか』で、「全ての生き物は、偶然、勝手に、利己的に生まれるが、死ぬときには、結果として他を利するかたちで、公共的に死んでいく」と述べる。一方で本書は、ヒトの場合は、他の野生動物のような現役バリバリか死かとは違って、その間に「老い」を実感し、物事をバランス良く見られる「シニア」というステージがあるという。シニアは社会にとって必須な存在であり、遺伝学的な見地、社会的な見地から、老いの正体、シニアとしての過ごし方を詳述してくれている。シニアにしかできない事を求める楽しみが湧いてきた。2023/08/02
ひこうき雲
46
人間は生物学的に55歳が寿命。医学の発展やらで85歳まで生きてる人が多い。 じゃあ与えられた30年間で何をする?おじいちゃん、おばあちゃん仮説(老いた人がいる方が集団の維持や子育てが上手くいく)について語られているけど、ただ隠居してるだけじゃ疎まれて、ご飯食べられないよね。ってだけじゃないかな。2023/11/23
シリウスへ行きたい
28
読み終えてしまった。少しづつ、例えば、今日は、「はじめに」、次の日は、「第1章」とかいって一週間ぐらいで読み終える。今回も、そのつもりが他の人から予約が入って、少しでも早く読まなくてはと思い、読みだすと早かった。生物学者の本なので、そっちの方の詳しい専門的なことは理解しがたいし、面白くないので、半分飛ばした。後半に入ると、社会的に、ヒト(人間)がシニアになる、いわば無用の存在となりながら他の生物と異なって、なぜ生きながらえることができるのか、またどういきるべきなのかを論じている。ひとそれぞれではある。2023/08/29
特盛
25
評価3/5。前作「生物は何故死ぬのか」に続き、生物学者から見た人の老化がテーマ。老化のメカニズム、他の生物との違い、進化的意義、筆者から見た生き方の提言が述べられる。7-8割方は前著のメッセージ、残りはシニアになった筆者のエッセイ的印象か。成田悠輔の老人切腹論への反応か、社会はシニアを大事にすべき、シニアは公共を意識して生きるべしが終盤の強い主題。自分もシニアになり行く故興味深いが、社会の変容が急激であり、シニア比率も社会が未体験に高くなる。老害にならずどう公共に貢献するか?は改めて難しい問いだと思った。2024/03/28