内容説明
「古池や蛙飛び込む水の音」芭蕉のこの俳句を英語で説明するとき、「蛙」をa frogとfrogsのどちらで訳すべきだろうか。単数か複数かを決めないまま翻訳することは英語では許されない。ほかにも「ちらちら」「どんどん」などの擬音・擬態語、「雨ニモ負ケズ」の漢字カタカナ交じりの表記、「顔が能面のようだ」といった比喩など、翻訳困難な日本語表現を紹介。夏目漱石も村上春樹も登場する、海を越えた日本語論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
58
有名な和文と訳された英文を並べ比較することで、日本語の多様性があらわになる。読点のリズムなどは念頭になかったため勉強になった。翻訳の凝縮された苦労に触れた感じがした。2018/07/29
501
25
日本語とはどういう言語なのか、日本語から英語への翻訳を通して理解する本として読んだ。特に英訳することで日本語のどのような部分が失われるという視点により、日本語の姿が見えるようになっている。学術的というより、言葉が持つウチ側/ソト側という視点に絞り、文例は村上春樹や夏目漱石、倉橋由美子らの文書を使用し、読者にとって入りやすいように考慮されている。「できる」は「can」と訳されるけど、言葉の奥に潜む概念は異なるなど興味深い内容だった。2019/01/06
Yuuki.
24
私は、日本語の文章を書いたり読んだりしている時に、「てにをは」の使い方に引っかかりつつも、何故それがしっくり来ないのか分からなかったり、同じ単語でも漢字よりも平仮名を使いたい気がするけれど、その理由が分からなかったりする事が多々ある。母語だからこそ無意識に使い分けている日本語。この本は、その日本語話者の言葉の感覚を、英語と比較しながら解説してくれるので、様々な事が腑に落ちて気持ちが良かった。2020/08/29
Fondsaule
20
★★★★★ 第1章:こぼれ落ちる響き、第2章:ひらがな、カタカナ、漢字、第3章:比喩は翻訳できるのか、第4章:過去の話なのに、現在形?、第5章:日本語の数はおもしろい、第6章:「ですます」が「である」に替わるとき、第7章:受動文の多い日本語、能動文の多い英語、第8章:翻訳に見る「日本語」の文体。【a】トムは日本語が話せます。【b】トムは日本語を話せます。英訳はどちらも、Tom can speak Japanese. 英語にすると同じになってしまう。でも同じじゃない。非常に興味深く、面白い。 2018/11/12
kaze
15
タイトル通りの本。過去形と現在形の話、受動態の話は特に興味深かった。受動態の本質は「自発」という指摘にはなるほどと思った。外国語(英語)は受動態を嫌う言語だと書いてあったが、イタリア語の再帰動詞などは自発のニュアンスがあるのではないか?と思いついてみたり。2022/04/13
-

- 電子書籍
- 私と夫と夫の彼氏 分冊版 51巻 ゼノ…
-

- 電子書籍
- 旦那のアレ、もらってください【タテヨミ…
-
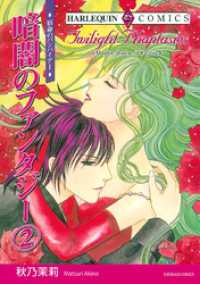
- 電子書籍
- 暗闇のファンタジー 2巻【分冊】 10…
-
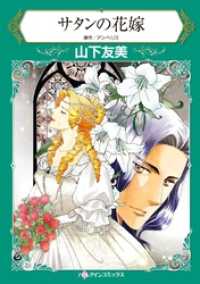
- 電子書籍
- サタンの花嫁【分冊】 4巻 ハーレクイ…
-
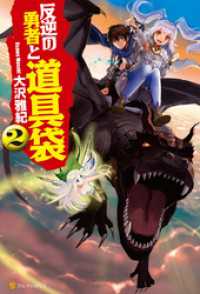
- 電子書籍
- 反逆の勇者と道具袋2 アルファポリス




