内容説明
0と1で世界のすべてを記述することは本当に可能か。デジタルの限界が露わになる時、アナログの秘めたる力が回帰する――。カヤックビルダーとしても著名な科学史家が博覧強記を揮い、ライプニッツからポストAIまで自然・人間・機械のもつれあう運命を描く
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Meme
14
監訳者解説の一部を読んで、なんとか頭では理解できたような気がしています。「まだわれわれが意識していない未知の原理にどう向かうかは、デジタルを超えた、いわゆる現在はアナログという言葉で一括りにされている何かなのだ」「テクノロジーが自然を模倣すしながら高度化することで、デジタル化したはずの社会がより自然に近いアナログな姿に回帰していく」多くのテクノロジストが、自然と触れ合う一面を大切にしている背景は、こうした側面にあるんではないかと思いました。2023/06/08
あつお
11
コンピュータの抽象化。 コンピューターの未来はアナログにあると本書は示す。①現代のデジタルコンピューターはエネルギー消費が大きく、人間のような抽象的な思考には限界がある。②現在のAI技術は複雑な並列処理に依存し、高エネルギーを消費する。③量子コンピューターは0と1の間の領域を扱い、より人間的な特性を持つコンピューターへと進化する可能性がある。この革新がアナログ的接点を増やし、抽象化を進めるだろう。2024/08/04
つかず8
8
本書は、デジタルとアナログを単なる対立概念ではなく相互補完的な存在として捉え、現代テクノロジーやAIの限界を超える新たな可能性を探る意欲的な一冊である。特に「無限」の捉え方を通じて、アナログ的思考の重要性を強調し、デジタル一辺倒の社会に対する批判と再考を促している。歴史や哲学を織り交ぜた構成は難解だが、深い示唆を含んでおり、再読によって理解が深まる内容である。2025/04/18
てら
7
今の私にとっては冗長に感じる本だった。訳者解説を読むとその謎は解けたし、冗長に感じた部分も意味があることが頭ではわかった。デジタルとアナログと我々の世界について述べてある。副題にAIの次に来るものとある。読了したが頭の中はハテナのままである。巷に溢れるAIに仕事取られるてきな安直な内容でないことは確か。アナログを連続するものと捉える。そして、あるものとあるものの関係性は常に変化し、それをアナログとするのであれば、ディープラーニングはアナログに足を踏み入れていて......てこと?わからん。再読必須。2024/08/11
coldsurgeon
6
難しい命題を持った本だった。デジタルコンピューティングが興隆し全盛期へと、そして更なるステップアップを迎えるかもしれない時代において、デジタルのもつ限界とその先に生まれるかもしれなアナログコンピューティングの世界を垣間見る必要はある。デジタルは2進法に始まり、その起源は古代中国の易経の六四卦にあるという。17世紀のライプニッツによる2進法による計算機の提案がコンピューター開発の始原にもなっている。デジタルは数えることが可能な2進法ではあるが、自然界は数えることができない実数系なので、アナログへ進むのだろう2023/06/03
-
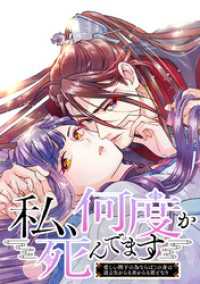
- 電子書籍
- 私、何度か死んでます~愛しい陛下の為な…
-

- 電子書籍
- 六本木クラス~信念を貫いた一発逆転物語…
-

- 電子書籍
- これも全部あの夏のせい(フルカラー)【…
-
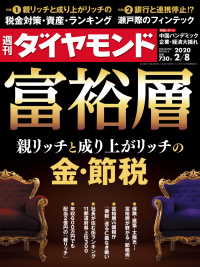
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 20年2月8日号 週…
-

- 電子書籍
- もう、止まらないからここで…【マイクロ…




