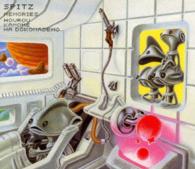内容説明
科学のすぐれた成果を照らす光は、時として「研究不正」という暗い影を生み落とす。研究費ほしさに、名誉欲にとりつかれ、短期的な成果を求める社会の圧力に屈し……科学者たちが不正に手を染めた背景には、様々なドラマが隠されている。研究不正はなぜ起こり、彼らはいかなる結末を迎えたか。本書は欧米や日本、中韓などを揺るがした不正事例を豊富にとりあげながら、科学のあるべき未来を具体的に提言する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
46
社会不正も研究不正もその根底では同じ。不正の底流は、真実への誠実の欠如、野心、競争心、金銭欲、こだわり、傲慢、責任感のない行動、ずさんな行為(ⅳ頁)。信頼回復に科学者は研究とは何かを見つめ直し、再認識するほかない。不正の実像をとらえ、対策を、という(2頁)。誠実な、責任ある研究(4頁~)。本書の目的:不正者の追及でなく、事例から学ぶこと(13頁)。21事例の最後に、HO(小保方晴子)氏によるSTAP細胞のねつ造が確実になった経緯が書かれている(103頁~)。笹井氏自殺は今なお謎のまま(117頁)。2016/08/11
リキヨシオ
32
STAP細胞、神の手、ノバルティス事件など世界で起きた研究不正42の実例の説明。研究不正とは何か?誰が研究不正を犯し何故彼らは不正に手を染めたのか?そして研究不正をなくすことはできるのか?様々な視点で研究不正について述べた1冊。数多くのノーベル賞受賞者を輩出した日本の独創的な研究、その一方で少なくない数の研究不正が起きていて研究不正による論文撤回の数…日本は第3位になっている。研究不正には、捏造、改ざん、盗用などがある。高い専門性に閉鎖された環境と数多くの誘惑…研究不正をなくすのは事実上不可能と思った。2016/10/05
zoe
27
毎年4月は情報教育係だったけれど、今年は転勤し、新たな職場で、受ける側。何か物足りず、この本を購入してみた。論文撤回が多い国は、研究先進国。例えばねつ造が多い。研究発展途上国は2重投稿や盗用が多い。事実を丁寧に記録していくことが、後日、再現性を確認するための基本。どうやって防止するのか。研究倫理教育。風通し良い研究室運営。情報の共有化と透明性。不正をしても、結局良いことは何一つ無い。捏造。改竄。盗用。2019/06/04
蜻蛉切
22
代表的な事例を挙げた解説と、研究不正の起きるメカニズム(原因)、論文発表の際のシステム等々、多岐にわたる解説で、門外漢にも分かり易かったように思う。 他人の論文だけでなく、自分の論文からの引用も、やり方によっては「盗用」「不正」となってしまうというのは意外であった。 やはり、不確かな要素(あやふやな要素)が入り込む余地が大きい分野ほど、研究不正や論文撤回が多くなるようである。 倫理教育や情報の共有など様々な方策はあるが、人が絡む限り不正の根絶は難しいのかもしれない。2018/06/02
Akihiro Nishio
20
元学長の本。良くこんな立派な人が東大から岐阜に学長として来てくれたもんだと改めて感謝。社会科学系の自分には、そこまでして不正をする理由はぴんとこないが、逆に自然科学系はここまできっちり研究を統制しているのかと感心した。自分の領域では、データをねつ造して発表する意味がほんとんどないが、他山の石とせず、自然科学系の厳密なデータ管理の方法をもっと見習った方がよいだろう。本書でも述べられているが、上位30大学の教員の平均的な論文生産量は1年に1本。なのに、なぜ1000を超える論文をねつ造してまで作ってしまうのか謎2016/09/09
-

- 電子書籍
- 「意味順」でまるわかり! どんどん話す…
-
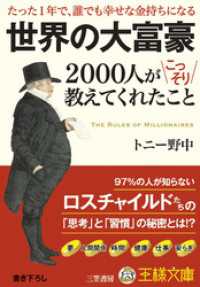
- 電子書籍
- 世界の大富豪2000人がこっそり教えて…