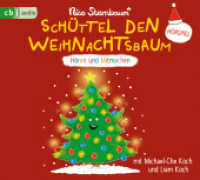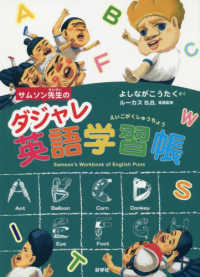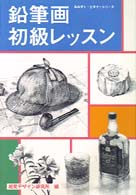内容説明
感想から解釈へ、感動から批評へ飛躍するために。脱構築批評からフェミニズム批評、システム理論、そしてエコクリティシズムまで。 20 世紀から現代までの理論を幅広く学び、具体的な作品分析をとおして批評のプロセスも体感できる入門書。
目次
はじめに
Ⅰ 記号と物語
第1章 構造主義(下澤和義)
第2章 物語論(赤羽研三)
第3章 受容理論(川島建太郎)
第4章 脱構築批評(巽孝之)
コラム 法と文学(川島建太郎)
Ⅱ 欲望と想像力
第5章 精神分析批評(遠藤不比人)
第6章 テーマ批評(小倉孝誠)
第7章 フェミニズム批評(小平麻衣子)
第8章 ジェンダー批評(小平麻衣子)
第9章 生成論(鎌田隆行)
コラム 研究方法史の不在(小平麻衣子)
Ⅲ 歴史と社会
第10章 マルクス主義批評(竹峰義和)
第11章 文化唯物論/新歴史主義(山根亮一)
第12章 ソシオクリティック(小倉孝誠)
第13章 カルチュラル・スタディーズ(常山菜穂子)
第14章 システム理論(川島建太郎)
第15章 ポストコロニアル批評/トランスナショナリズム(巽孝之)
コラム 文学と検閲(小倉孝誠)
Ⅳ テクストの外部へ
第16章 文学の社会学(小倉孝誠)
第17章 メディア論(大宮勘一郎)
第18章 エコクリティシズム(波戸岡景太)
第19章 翻訳論(高榮蘭)
コラム 世界文学──精読・遠読・翻訳(巽孝之)
あとがき
参考文献
事項索引
人名・作品名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K(日和)
13
私がやっているのは「テーマ批評」「ジェンダー批評」「ソシオクリティック」「クィア批評」「文学の社会学」「カルチュラル・スタディーズ」「ポストコロニアル批評」をかいつまんでいると言えそうだと理解した。それぞれ辿ってきた文脈があるため、ツールを使うときに原典を含め適宜参照したい。私が朧げにやっていることが体系立てて設計されているとわかった。2024/04/28
ラウリスタ~
12
文学理論の教科書として最新であり、フランスに偏らずに、英米独、さらにはフェミニズム、エコクリティシズム、日本帝国時代の日本語(翻訳論)など、アクチュアルな問題にもしっかり触れている。分野横断的な執筆陣の良さが随所に感じられる(文学理論ってフランスvs英米というイメージだが、当然それだけじゃないわけだ)。各章の前半で理論と歴史的展開、後半でいくつかの作品に基づいて実践的読解なので、わかりやすい。12章「ソシオクリティック」は文学作品内部で表現された社会・歴史など、16章「文学の社会学」は流通など作品の外部。2023/08/11
masabi
8
【概要】各理論の概説と理論を使って作品を読解する実践からなる。【感想】実践では小説以外にも演劇やアニメ作品も対象にする。哲学、社会学、精神分析など他の学問の成果や刺激を取り入れた理論や提唱された当時の問題意識などを知ることができた。2023/09/02
さとまる
4
図書館本。お手上げ。文学理論について知りたくて手を出してみたのだが、今の私にはレベルが高すぎて何が書いてあるのかすらわからなかった。かろうじてわかった部分も理論に基づいての批評と言うよりも、先に言いたいことがあり後付けで理論を構築した牽強付会のように感じてしまう。そもそも「批評」というものに対しての無理解が私にあるのかもしれない。2025/01/04
稟
3
19の批評理論を研究者たちが10頁程度でその概略と理論を用いた作品の分析をしてみせ、理論と実践の往還を示す。理論とは方法論であり、それをどのようにあてがうか、すなわち個々の作品をといかに読み替えられるか、という点にその価値を見出せるのだろうが、扱う作品の多くが海外の作品というのが類書の常であった。しかし本書は村田沙耶香、古川日出男などの作品分析でそれを行う。中でも卓越しているのはマルクス主義批評を担当した竹峰義和。ジブリの代表的な三作を見事に読み替えてみせた。このような入門書が増えるといいのだが。2023/04/30
-
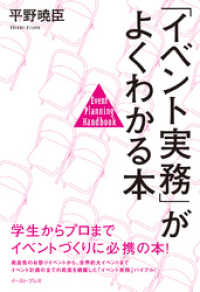
- 電子書籍
- 「イベント実務」がよくわかる本