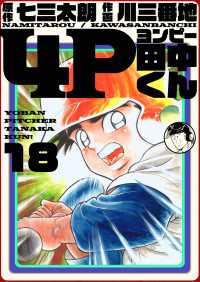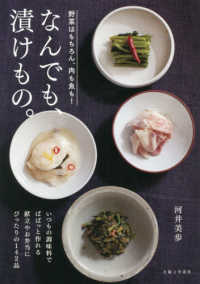内容説明
国会でも会社でも商店街の会合でも
そして学校のなかでも、
人間の行動には同じ力学=「政治」が働いている……
いまを生きるわたしたちに必要なのは
半径5メートルの安全保障 [安心して暮らすこと] だ!
学校生活のモヤモヤを政治学から見てみると、
わたしたちはとっくに政治に巻き込まれていた!
◆自治:女子の靴下だけ黒限定のトンデモ校則
◆議会:かみ合わなくてイライラがつのる学級会
◆多数決:むりやり感あふれる過半数ルール
◆公平:不登校を「ズルい」と思ってしまう気持ち
◆支持:意見を言えない人はどうする?問題
心をザワつかせる不平等も、友だち関係のうっとうしさも、孤立したくない不安も……
教室で起きるゴタゴタには、政治学の知恵が役に立つ!
学校エピソードから人びとのうごめきを読みといて、社会生活をくぐりぬけていこう。
人が、社会が、政治が、もっとくっきり見えてくる。
「安全保障、といっても軍備や国家間の紛争の話をしようというわけではない。半径五メートル、それは僕たちの日常の生活空間の話だ。日常の生活空間(とくに教室内)で頭を抱えながらうずくまるのではなく、少しでも心穏やかに、安心して過ごすために、なにより政治学が役に立つ、ということを伝えたいのだ」
(「はじめに」より)
【目次より】
はじめに
序章 大前提――力を抜いて自分を守る
――善・悪・社会
教室のなかの安全保障/だれも立派にはなれません/友だちが一〇〇人も必要なワケがない/世界史に一度しか登場しない僕たち
第1章 言うことを聞く/聞かせるということ
――権力・合意・自治
政治とは「選ぶ」こと/僕たちの心の習慣――理由を放置したまま従う/トンデモ校則は守るべき?/「みんなで決めた」というフィクション
第2章 どうして「話し合い」などするのか
――議論・中立・多数決
話し合いは失敗する/偏りを確認するために/「論破」に含まれているもの/多数決=民主主義?――とりあえずの風速計/黙っているが考えている/言い出せない人のための政治
第3章 仲間をつくるということ
――対立・支持・連帯
友だちより「仲間」を/対立を恐れず、やみくもに戦わず/上も下もない対等な僕たち――協力関係の組み立て
第4章 平等をめぐるモヤモヤ
――公平・公正・分配
心がザワつく厄介な「平等」/平等を切り分けてみる/平等でないと困る理由
第5章 政治は君たちの役に立つ
――責任・民主主義・政治
自己責任論なんて無視してよいのだ/やり直しが前提のシステム――民主主義/学校でも家でもない場所へ
おわりに
大人はなかなか変わりにくい/こんな世の中にしてしまった/政治学は教室を放置してきた/僕たちもかつては君たちだった
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Rie【顔姫 ξ(✿ ❛‿❛)ξ】
Mc6ρ助
トト
manabukimoto
みさと