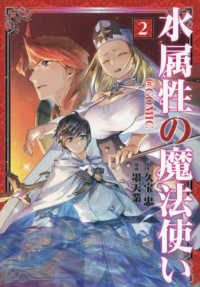内容説明
知的財産法の世界では、近年のめざましい技術の進歩を背景として、パブリック・ドメインとの境界線上における紛争が多発している。本書では、従来あまり重視されてこなかったパブリック・ドメインを中心に据えて、創作の奨励や産業・文化の発展のため、いかにしてパブリック・ドメインを豊かにし、その利用を確保するのかという観点から、各種の知的財産法の構築を目指す。
目次
はしがき[田村善之]
第1部 総論
第1章 特許制度における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋[田村善之]
I 問題の所在:創作物アプローチvs.パブリック・ドメイン・アプローチ
II 特許制度における課題
III 権利の入口の場面における相剋
IV 権利の出口の場面における相剋
V 結びに代えて:権利の出口と入口のインタラクティヴな関係
第2部 特許要件
第2章 特許適格性要件の機能と意義に関する一考察[田村善之]
I 関連規定
II 自然法則の利用の要件の淵源
III 事例研究
IV 解釈論の構築
V 新規性・進歩性要件との関係
VI 結び
第3章 用途発明の意義──用途特許の効力と新規性の判断[前田 健]
I はじめに
II 用途発明の意義
III 用途発明の特許権の効力
IV 用途発明の新規性
V おわりに
第4章 パブリック・ドメイン保護要件としての新規性/進歩性の再構成──内在的同一について特許を認めたロシュv.アムジェン事件を端緒として[吉田広志]
I 特許要件は何のために存在するか?
II 内在的同一におけるPDと特許権の調整
III 従来の裁判例
IV 検討
V 終わりに代えて
第5章 AIと進歩性──若干の問題提起[中山一郎]
I はじめに
II 従来の議論
III 問題の所在
IV 米国の先行研究
V 若干の検討
VI おわりに
第3部 侵害の成否
第6章 「広すぎる」特許の規律とその法的構成──クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性[前田 健]
I はじめに
II 「広すぎる」特許はどのように処理されてきたか
III 「広すぎる」特許はどのように処理すべきか
IV 保護の限界としての「明細書に開示された技術的思想」
V おわりに
第7章 クレイム制度の補完としての均等論と第5要件の検討──第4要件との関係から考えるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの相克[吉田広志]
I 方法論としてのクレイム制度とその功罪
II マキサカルシトール最高裁判決
III 補正・訂正と第5要件──コンプリート・バーかフレキシブル・バーか
IV 第5要件と第4要件との関係
V コンプリート・バー/フレキシブル・バーに関する裁判例──その1・否定例
VI コンプリート・バー/フレキシブル・バーに関する裁判例──その2・肯定例
VII 試論・あるべきフレキシブル・バーの高さを巡って
VIII 結びに代えて
第8章 特許法の先使用権に関する一考察──制度趣旨に鑑みた要件論の展開[田村善之]
I 問題の所在
II 先使用権制度の趣旨
III 発明の完成・事業の準備
IV 発明の同一性
V 実施形式の変更の可否
VI 結びに代えて
第4部 救済
第9章 特許権侵害に対する差止請求権の制限に関する一考察[鈴木將文]
I 本稿の目的
II 特許制度における差止請求権の意義
III 我が国の動向と課題
IV 国際的動向
V 検討
第10章 COVID-19パンデミックにおける公衆衛生と特許──TRIPS協定ウェイバー提案を踏まえて[中山一郎]
I はじめに
II 公衆衛生と特許権の関係
III COVID-19パンデミック下での医薬品アクセスと特許をめぐる動向
ほか
-

- 電子書籍
- 双子兄妹のニューライフ【タテヨミ】第1…