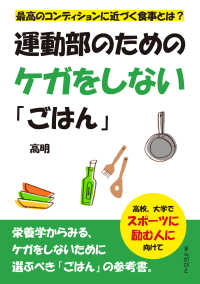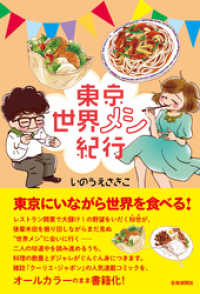内容説明
日本人はなぜ、こんなにもポテチが好きなのか?〈アメリカ〉の影、〈経済大国〉の狂騒、〈格差社会〉の波……。ポテトチップスを軸に語る戦後食文化史×日本人論 /『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ─コンテンツ消費の現在形』で注目の著者、待望の新刊!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
168
ポテトチップスに思い入れなど一切ないが、あの「映画を早送りで観る人たち」で感心した稲田さんだからと手にした一冊。ポテトチップス一つで、これだけ多様な考察ができるこの著者は只者ではない。ポテトチップスは油の劣化で鮮度が落ちる生鮮食品であり、原料の収穫に左右される季節商品だという。そんな課題を克服した湖池屋さんとカルビーさんの切磋琢磨は、産業論として十分面白い。多様なフレーバーを提供する日本のポテトチップスは「欲望の充足装置」だと言う。貧者のパンとして蔑まれてきたジャガイモを、国民食にまで高めた歴史に胸躍る。2023/07/04
パトラッシュ
158
今やポテトチップスは国民食とされているが、当たり前にありすぎて誕生や普及の経緯など気にもとめずに来た。そんなポテチがどうして作られるようになったのか、日本人をポテチ好きにするために生産者がどんな工夫を重ねたか、企業間の販売競争や技術開発などの知られざる裏話が満載の実に面白い本になっている。いろいろ食べてきた新製品が出た裏話や、経済情勢や国民生活の変化に伴って求められる味が変わっていく様子は、同時代に生きた者として思わず「そうだったのか」と膝を叩く話も多かった。ポテチは日本の戦後史に寄り添った同伴者なのだ。2023/06/22
アキ
132
英語圏でpotatoとはつまらない人、愚かな人という意味合いを含む。ジャガイモを食べる人々とはアイルランド人を指す差別用語だった。Couch potatoとはカウチにジャガイモのように寝そべって、テレビの前から動かない怠惰さを表すらしい。本書は主に湖池屋の立場からカルビーとのポテトチップスの新商品の争いを時系列で示してして、まさに自分史と重なる部分が多くて面白かった。カルビーのコンソメパンチと湖池屋のカラムーチョ世代だが、マツコデラックスに取り上げられ注文が殺到した菊水堂のポテトチップスって食べてみたい。2023/07/14
Aya Murakami
111
図書館本。若い人に贈る読書のすすめ2024。 ポテトチップスと戦後日本史(濱田音四郎の部分ちょっとだけ戦前戦中史)な一冊。 ポテトチップスといえばスイーツよりも一段劣る(甘くないからね)お菓子というイメージでしたが、どうやらヒトの味覚は豊かになると甘いものよりもしょっぱいもの、辛いものに好みがうつるそうな。と…いうことは甘党の私は貧しい味覚ということなのか?なんかイヤだなぁ。 ポテトチップス用(?)のジャガイモが料理用のジャガイモとは別に用意されているというのは初耳。修学旅行の時のジャガイモ畑を思い出す。2024/08/21
fwhd8325
89
家が商売をしていましたので、湖池屋がのり塩味のポテトチップスを発売したことはよく覚えています。少し濃いめの塩味と青のりのバランスはとっても美味しく感じました。後発のカルビーがポテトチップスを販売していたのもよく覚えています。だけどカルビーのポテトチップスは、あまり美味しく感じませんでした。そんな話はさておいて、この著書は面白かった。ポテトチップスは、日本人の国民食になったのかもしれません。私の一番の推しは、今は販売されていない無印の青のり。これに勝るものはいまだに見たことがありません。2023/07/08