内容説明
現職のインド外相がその「手の内」を明かす
本書は、台頭著しいインドがどのような外交を展開していくのか、そして変貌する世界の中でどのような役割を果たしていくのかについての見取図を示したものである。著者は、インドの現職外務大臣(2019年の第二次モディ政権発足時に就任)。もともと外交官としてインド外務省で駐米大使や駐中国大使をはじめ要職を歴任し、事務方トップの外務次官を務めた。
本書では、多極化する世界の中で国益を冷徹に追求するとともに国際的地位の向上をめざし、国際社会との調和を図っていくというインド外交の要諦が明確に論じられている。ときに叙事詩『マハーバーラタ』を援用して、友好と競争が併存する国との接し方や二国間関係のパワーバランスを変えるための外部要因の活用法など含蓄に富んだ外交論を展開する一方、日米豪が推進する「インド太平洋構想」に対していかに関わっていくかについても別途一章を立てて詳述する。「インドならではの手法」とは何か――現代インドの政治・外交に内在する論理・思考を理解するための必読書だ。
齋木昭隆氏(元外務事務次官・日印協会理事長)推薦!「インド外交の過去・現在・未来がこの一冊で的確に示されている」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
紙狸
22
原著2020年、翻訳22年の刊行。著者S・ジャイシャンカル氏は、モディ政権の外相。もともとはキャリア外交官。この本はシンクタンクなどでの講演をまとめた。教養のある外交官がレベルの高い聴衆向けに語ったもので、中身は柔らかくはない。訳注が簡にして要を得ており、解読を大いに助けてくれた。インドが大国として台頭していくことは確実だとした上で、「問われているのは、不確実性が高まる時代において、いかにしてそれを最適なかたちで実現するか」だという。マハーバーラタをひいた章はインドの「戦略文化」の一端を伝えようとする。2023/06/29
papacy
9
【日印は似た境遇】米ソ冷戦のハザマで揺れ動き、今や人口世界一になったインド。著者はチェコ、中国、米国大使を歴任し、近年モディ首相に抜擢されて外相に。インドと日本は似た境遇と言う。ASEAN諸国への向き合い方、安倍さんのインド太平洋構想、目前の利益でなく総合利益を狙う姿勢、保護主義米中への対峙など。過去20年、中国は流血せず貿易で勝利し、米国は勝利なしに戦い続けた。結果、米国は弱り中国が力を持ち過ぎた。日本にはプレゼンスを取り戻して欲しい、インド進出で中国に負けないイニシャチブを期待すると著者は締めくくる。2025/05/31
かなた
5
欧米に迎合することなく、アジアの一つの大国として実利主義を貫いている。インドは200年に渡り占領されてきたが、その憎悪を政治利用してこなかった点で、中国と違う。これからの国際社会を担う大国となることがほぼ確実のインドから目が離せない。2023/09/12
takao
3
ふむ2023/05/18
海冨長秀
3
インドについて詳しくないので日本が出てくるところしか楽しく読めなかった。インドはバーフバリやムトゥという大変面白い映画を見たくらいなので、神話や歴史について知ってから再読したい。印象に残った箇所はp200「日系企業はインドがビジネスのための理想的な環境を提供してくれるのを待つのではなく、それを自ら形成すべくさらなるイニシアチブをとってもらいたい。」NHK日曜討論で元外務省の出演者が米国からも「日本が米国に何をしてほしいのか、主張してほしい」とよく言われると言っていたのを思い出した。2023/02/16
-
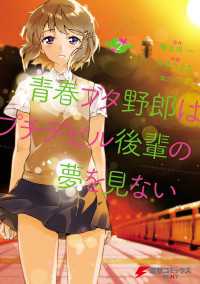
- 電子書籍
- 青春ブタ野郎はプチデビル後輩の夢を見な…




