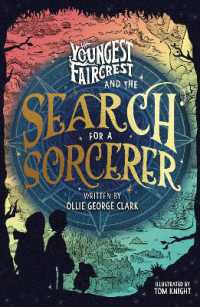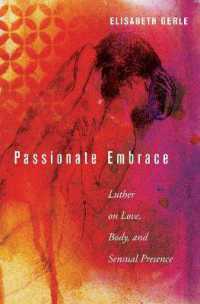内容説明
人は、物語に救われてきた。なぜ?
世界文学を人類史と脳神経科学で紐解く
――米国では出版権が6桁競売に。文理融合の教養書、上陸
小説や詩を読んで心が癒された。そうした経験を持つ人は多く、「文学は心に効く」とはよく言われることである。しかし、それは本当なのか?文学作品が人間の心に作用するとき、我々の脳内では実際に何かしらの変化が起きているのだろうか?
神経科学と文学。その2つの学位を持ち、スタンフォード大学でシェイクスピアを教える著者が、文学が生み出した「人を救済する25の発明」と、その効能(実効)を解説する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かもめ通信
22
自分の読書観を変えるほどの衝撃を受ける本とは、そうそう出会えるものではない。それなりに長くなった私の読書人生の中でも、指折り数えて片手で足りるほど。けれどもこの本はきっと、私の今後の読書人生を大きく変えることになるだろう、そんな予感がする。2023/04/20
木麻黄
4
人はなぜ文学に惹かれるのか。映像技術がいかに進化しても,本から得られるような心理的インパクトを獲得するのは難しいような気がする。考えてみれば,単なる文字の羅列が,時には人の孤独を癒し,悲哀を慰め,決然たる勇気を呼び起こすのは,不思議と言えば不思議だ。脳に内蔵される生きる力が,本に内蔵されるパスコードによって,静かに駆動するからだと筆者は説く。それが本当かどうかは,正直言って多少胡散臭くは感じてはいるのだが,読書によって脳機能の更新がされることを私自身は信じている。読書案内としても読める,夢のある論考です。2025/06/16
fumisikimi
3
脳神経科学で文学を解剖する!みたいな内容で文系を威圧する大著なのかと思ってたら意外と読みやすく、読書レベル低の自分でも良く読めた。脳神経科学の部分は専門的な書き方はしてないし気になる章から拾い読みできる。私にはとても刺激的で楽しい文学入門となった。 それで色々拾い読みをしながら付録や出典に目を通すとハッとするんだけど、本書の著者さんは物語科学という、アリストテレスの「詩学」にルーツを見出せる変わったジャンルの方らしい。どうりて有名な作品にこんなアプローチをするんだなという解説が多いなと思った。面白いです
袖崎いたる
2
発明に焦点を当てた、文学作品の読解。これはアリストテレスの『詩学』の、それも復元されたそれを通して発見された、ソフィストのあり方に立脚している。遡るかたちで辿ると、哲学者、修辞学者、文学者といった具合。最後のソフィストての文学者が歴史のなかで埋没してった。最近になって考古学されたのが原初のソフィストというわけ。これは人間をエンパワメントする文学のテクノロジーを認識させるようにする解釈格子で、この本は人類史のなかの文学営為のうちに発明されてきたテクノロジーを紹介する。説得材料に脳の話をするのは、ちと違和感。2025/02/24
dexter4620
1
文學の歴史を紐解きながら、培われてきたテクニックを解説する良書。文筆家はこういうテクニックをそれぞれ習得して、メシを食っているのだろうかと気になる。批判もあるようだが、脳科学を活かした解説や見解も有益。700ページ超の大作だが、読んでよかった。2026/01/13