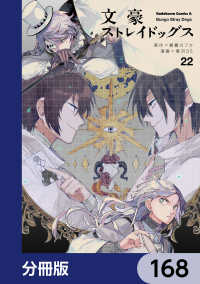内容説明
近代および現代の作家や文学者そして画家たちの作品と「落語」「落語家」「寄席」にまつわるひろく世に知られた事象から著者(天満天神繁昌亭支配人)が探り当てた事柄まで多岐にわたる逸話と蘊蓄。
「産経新聞」(夕刊、連載継続中)と「大阪保険医新聞」に連載されたコラム「落語×文学」と「作家寄席集め」を1冊にまとめる。取り上げた作家および文学者は、坂口安吾、永井荷風、芥川龍之介、森 外、織田作之助、武田麟太郎、谷崎潤一郎、吉井勇、江戸川乱歩、太宰治、内田百閒、正岡子規、吉村昭、折口信夫、久保田万太郎、直木三十五、塚本邦雄、色川武大、富士正晴、藤沢桓夫、井上ひさし、宇野浩二、星新一、永井龍男、坪内逍遥、向田邦子、久米正雄、秋田實、田村隆一、田辺聖子、周作人、野坂昭如、池内紀、吉行淳之介、田河水泡、鍋井克之、徳田秋声、小松左京、宮本百合子、横溝正史、岡本綺堂、和田誠、中江兆民、小島政二郎、安野光雅、半村良、開高健、渋沢栄一、幸田露伴、手塚治虫、丸谷才一、小沢昭一、古井由吉、瀬戸内寂聴、松崎天民、石原慎太郎、辻潤、司馬遼太郎、山口瞳、山崎豊子、二葉亭四迷、夏目漱石、山田風太郎、水原秋櫻子、南方熊楠、志賀直哉、齋藤緑雨、山本周五郎、泉鏡花……等。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
J D
62
総勢81名の文学者たちが登場する。坪内逍遥から始まり西村賢太さんで終わる。それぞれの落語との関わりから影響を与えた作品まで詳細に記載されながらも無駄なくコンパクトに紹介されていた。高校時代、現代文の授業中は、ほとんど「国語便覧」を読んでいた私には発見の多い読書となった。三代目小さんの記述があちこちに見られ、また、聴いて見ようと思った。「クスっ」という笑いをもたらす落語が文化としてある日本は素晴らしい国だと思った。古典文学と落語好きにはおすすめです。2023/05/13
ネギっ子gen
57
カルチャーセンター講座「漱石と落語」講師で天満天神繁昌亭初代支配人による、坪内逍遥から西村賢太まで近現代の作家たちの「落語、落語家、寄席」にまつわる逸話を集めた書。最初は『産経新聞』で、次は『大阪府保険医新聞』に連載したものを書籍化。<明治以降の作家たちの作品を読み取り、落語や寄席からの影響や関わりを探り報告するという作業は思った以上に興味を覚え、私の関心を広げました。それとともに落語という芸能が日本文学研究者にこれまでさほど振り向かれもせず、本格的な研究書も書かれていないことに気づかされました>、と。⇒2023/06/19
りんご
36
あ、そういう本なのね。江戸川乱歩、小松左京、井上ひさしなどなど81名の作家さんがどんなふうに落語に影響受けたか、親しんだかってエピソードがじゃらっと書かれてます。落語は娯楽なのでどのようにでも触れる機会があるでしょうが、リサーチがすごい。感服。2023/11/12
ayumu
1
勝手に敬愛している、恩田さんが本を出されたということで、早速購入して読んで見ました。文豪たちがこれだけ落語に魅せられたという事実に落語の偉大さを改めて実感。あと恩田さんの博学ぶりにも脱帽…。落語の良さを現代に様々な形で自分なりに広げていきたいと思いました。2023/08/01
tkm66
1
雑学レベルで堪能。2023/04/24