内容説明
インターネットは世の中の「速度」を決定的に上げた。
しかしその弊害がさまざまな場面で現出している。世界の分断、排外主義の台頭、ポピュリズムによる民主主義の暴走は「速すぎるインターネット」がもたらすそれの典型例だ。
『遅いインターネット』が主張するこの指摘はコロナ禍とウクライナの戦争が起こる中、悪い意味で加速している。いま改めて最新の分析と対抗策を大幅に加筆しついに文庫化。
インターネットによって本来辿り着くべきだった未来を取り戻すには、今何が必要なのか。気鋭の評論家が提言する。
解説:成田悠輔
―――――――――――――――
序章 オリンピック破壊計画
TOKYO2020
平成という「失敗したプロジェクト」
「動員の革命」はなぜ失敗したか
走りながら考える
第1章 民主主義を半分諦めることで、守る
2016年の「敗北」
「壁」としての民主主義
民主主義を半分諦めることで、守る
民主主義と立憲主義のパワーバランスを是正する
「政治」を「日常」に取り戻す
インターネットの問題はインターネットで
第2章 拡張現実の時代
エンドゲームと歌舞伎町のピカチュウ
「他人の物語」から「自分の物語」へ
「他人の物語」と映像の世紀
「自分の物語」とネットワークの世紀
『Ingress』から『ポケモンGO』へ
ジョン・ハンケと「思想としての」Google
仮想現実から拡張現実へ
拡張現実の時代
個人と世界をつなぐもの
物語への回帰
「大きな物語」から「大きなゲーム」へ
文化の四象限
第3章 21世紀の共同幻想論
いま、吉本隆明を読み直す
21世紀の共同幻想論
大衆の原像「から」自立せよ
「消費」という自己幻想
吉本隆明から糸井重里へ
「政治的なもの」からの報復
「母性のディストピア」化する情報社会
第4章 遅いインターネット
「遅いインターネット」宣言
「速度」をめぐって
スロージャーナリズムと「遅いインターネット」
ほんとうのインターネットの話をしよう
走り続ける批評
文庫版書き下ろし 新章
分断する社会とより「速い」インターネット時代への対抗戦略
1.コロナ・ショックと「速い」インターネット
2.なぜ人はウイルスを直視できなかったのか
3.パンデミックとデジタル・レーニン主義
4.プラットフォームの時代と、その罠
5.持たざる者たちの希望と絶望
6.金融資本主義とプラットフォーム
7.21世紀のグレート・ゲーム
8.回帰と加速
9.戦争と「遅い」インターネット
10.プロパガンダの本質
11.モノからコトへ、再びモノへ?
12.肉でも穀物でも酒でもなく、禁断の果実を
13.強い物事と弱い人間
14.プラットフォーム下の実空間
15.「庭」へ
16.SDGsの18番目の目標
解説:成田悠輔
-

- 電子書籍
- 異世界日本~暗殺一家の三男は異界化した…
-

- 電子書籍
- 蜘蛛ですが、なにか?【分冊版】 92 …
-
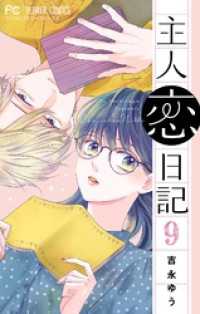
- 電子書籍
- 主人恋日記【マイクロ】(9) フラワー…
-

- 電子書籍
- 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者…
-

- 電子書籍
- メイドインアビス(5)【分冊版】34 …



