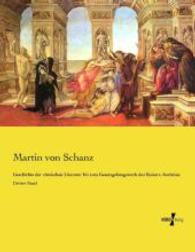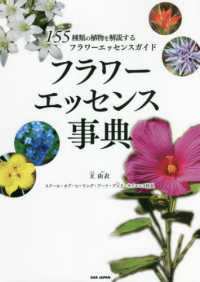- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
中国共産党総書記として異例の三期目に突入した習近平。幹部人事を意のままに行い盤石の体制に見えたが、コロナ対策では国民の反発で軌道修正を迫られ、一転、不安を感じさせる幕開けとなった。建国百年を迎える二〇四九年への中間点とされる二〇三五年に、彼は八十二歳。国内外の難問が山積する中国は、その時どうなっているのか? この国と中国共産党の本質を踏まえながら、第一人者が今後の行方を占う。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
85
著者は元駐中国大使(2006~10)。世間には中国脅威論を謳う本が溢れている。嫌中論に基づくものは論外としても冷静な学術的な本においても然りである。軍事力の増強は現実に違いないが、その真意・目的については今一つわからない。本書における著者の「中国の立場からはどう見えるのか?」という視点からの分析により、いろいろな事が腑に落ちる。習近平は毛沢東・鄧小平に並び立つ権威を確立しようとしている。党内民主の要求や国民の離反などの潜在リスクに考慮しつつ共産党による統治の正統性を常に示していくことは容易なことではない。2023/05/12
えちぜんや よーた
83
宮本雄二元・中国大使は感情保守でもないし、安易な「中国崩壊論」に与したりしない(だからこの本はちょっと難しい)。かといって2049年(中華人民共和国誕生100周年の年)に中国が米国を追い抜くかと言う問いにはNOを示す。自分もそう思う。中国は侮り難く、全体の国力としてすでに日本を凌駕している。だが国として米国を追い抜くことはない。中国は国民に物事を自由に考えたり発言することを許さない。胡錦濤の時代までは経済については自由な言論に寛容であったが、当代はそれすら圧殺してまう。そんな国に未来があるだろうか。2023/10/28
skunk_c
75
著者は中国大使も務めた元外交官。したがって中国政治の現場を深く知る立場にあった上、「外交のためには相手国を深く知らねばならない」として様々な角度から検討を加えているため、表面の出来事に一喜一憂したり、危機感を煽ったりする著作とは大きく異なる。基本は中国にとっての利益は日米を敵に回さないことという視点で首肯できる。現在の中国経済が何に支えられているかを見切れば当然と思う。その意味でリスクを増す東アジア軍拡については、さすが外交官で相手の出方を直接変えられないことを知悉しているため、安易な書き方はしていない。2023/07/15
鮫島英一
24
中国という国を元中国大使という経歴をもつキャリア官僚視点で解説している一冊。興味深かったのは習近平の思想を教え込むのは、思想を政策や行政レベルに落とし込む程度が官僚の理解度に左右されるという点だった。具体的な政策が先ではなく思想が先という統治形態は、共産圏らしいといえばらしいが興味深い。宮本氏を悪く言うわけではなくが、あくまでキャリア官僚視点でなので、現場の声からは遠い気がしないでもない。これから手に取る方は、橘 玲氏の「言ってはいけない中国の真実」などの作品も読むことでバランスを取ることを勧める。 2024/12/28
金吾
22
習近平に対する評価は流石だなあと感じました。しかしなんだかんだ言っても権力集中は進んでいるように感じますので、疑問もありました。外交の定義は納得できます。2024/08/11