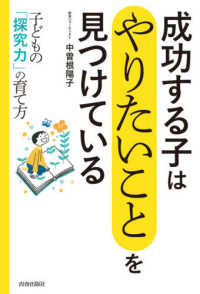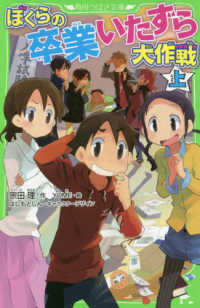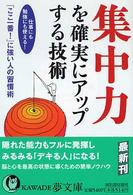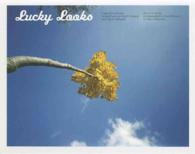内容説明
六一八年、李淵(高祖)が隋末の争乱の中から、唐を建国。太宗、高宗の時代に突厥・高句麗を破り、最盛期を築く。武則天、玄宗の治世は国際色豊かな文化を生み、大帝国の偉容をほこった。安史の乱以降は宦官支配や政争により混乱し、遊牧勢力と流賊の反乱に圧され、九〇七年に滅亡した。本書では、歴代皇帝の事績を軸に、対外戦争、経済、社会制度、宮廷内の権謀術数を活写。東ユーラシア帝国二九〇年の興亡を巨細に描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
133
遣唐使で知られる唐王朝三百年の歴史は、日本流にいえば戦国時代がずっと続いたようなものだ。武則天に国を一時乗っ取られ、有名な安史の乱のみならず年中行事のように内乱が発生し、殺し合いの権力争いが繰り返されたのだから。皇室自体が遊牧民族の血を引き、領土拡大の過程で大量の異民族を中国本土に招き入れ、ユーラシアの多民族国家と化していた唐は統治不能なカオスだった。そんな各勢力が科挙の浪人生をスカウトして法や制度を整備したことが、後の外来征服王朝の先駆けとなったとする。従来の中国史とは異なる新たな視点を提供してくれる。2023/05/09
六点
107
中華帝国としての唐ではなく、ユーラシア大陸における国家の一形態として捉え直した一書。2023/09/06
kk
47
唐朝一代の歩みを、主として政治史に焦点を絞って概説するもの。政治的イデオロギーとしての仏教等に触れている以外、経済・社会面での発展や文化面での時代的特色などは思い切ってオミットし、時代区分に関わるような論点には立ち入らず。反面、著者ご専門のソグドを中心に、エスニシティ的な要素に特別な注意が払われ、そうした視座から中央政権の担い手、各藩鎮の性格、唐朝と周辺民族の関係性等について興味深い考察を加えています。基本的には読み易く、オリジナリティも感じられて、それなりに楽しく読みました。2023/05/16
サアベドラ
44
7-10世紀の中華帝国・唐の勃興から滅亡までを描いた新書。2023年刊。著者の専門はソグド史。東ユーラシアの大帝国の名にふさわしいのは突厥を下した太宗の治世のみで、それ以降、特に安史の乱後は外は強大なウイグルとチベットとの抗争、内は半独立化する節度使や藩鎮、宮廷では腐敗した宦官や官僚に無能な皇帝と、グダグダと言う他ない状況が続く。唐を中心にしつつ東ユーラシア全体の動向にも目を配った記述は近年の中国史研究のトレンドを反映していると言える。これだけ盛りだくさんの内容をよく新書サイズにまとめきれたなと感心。2023/06/23
よっち
37
唐の時代をどう捉えるべきか。歴代皇帝の事績を軸に対外戦争、経済、社会制度、宮廷内の権謀術数を通じて、東ユーラシア帝国二九〇年の興亡を描く一冊。南北朝と隋から唐建国に至るまで、貞観の治と太宗の実像、武周革命、開元の治と玄宗の時代、安史の乱から変わる統治体制とそれに抗おうとする試行錯誤、そして黄巣の乱から滅亡に至るまで、それに突厥やチベット・ウイグルなどがどのような形で絡んできたのかも交えながら解説していて、それを踏まえて眺めてみるとなぜ長きに渡って続いたのか、違った側面も見えてきてなかなか興味深かったです。2023/04/17
-
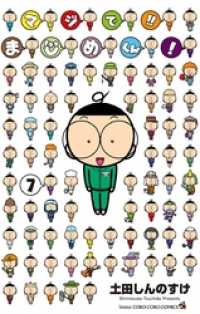
- 電子書籍
- マジで!! まじめくん!(7) てんと…
-
- 洋書
- Lucky Looks