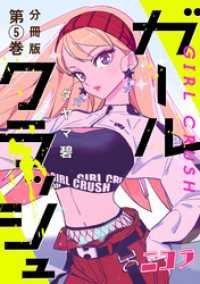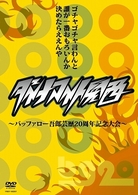内容説明
記憶(憶えとどめておく能力とそのための仕組み)と想起(特定の内容を再び呼び起こす動的な過程)は、教育および人間形成とどうかかわるのか。この問いに対し、教育哲学を足場として多様な視角から検討する。人間形成に関する学問と記憶の関係、書くことや記憶継承をめぐる問題について論じつつ、〈記憶の教育学〉モデルを構想する。
目次
はじめに──「記憶」が導く教育への問い[山名 淳]
第一章 記憶・想起と人間形成[ローター・ヴィガー/山名 淳 訳]
はじめに
一 ヨーロッパの哲学における記憶と想起
二 文化科学における記憶と想起の形式
三 想起と人間形成の対象としてのホロコースト
第二章 教育における「記憶」の意味転換──実験心理学的記憶研究の教育論への導入をめぐって[今井康雄]
一 消え去らない「記憶」
二 一九世紀ドイツにおける記憶と教育
三 実験心理学と記憶研究──ダンジガーの心理学史研究から
四 記憶をめぐる教育論──エルンスト・モイマンの場合
五 現代的な教育論の構図へ
第三章 「当事者」について記憶の観点から考える──当事者研究と現象学的質的研究を手がかりに[大塚 類]
一 問題の所在──「当事者」とは誰か
二 当事者研究における当事者と記憶
三 現象学的質的研究における意味と当事者性
四 現象学的質的研究における記憶と当事者性の拡大
五 「当事者」とは誰か
第四章 ハンブルクの「ゲニウス・ロキ」を想起する──アビ・ヴァールブルク「文化科学図書館」をめぐるビルドゥング・トポグラフィ[眞壁宏幹]
はじめに
一 ハイルヴィヒ通り一一六番地(Heilwigstrasse 116)
二 ドーム広場(Domplatz)
三 エドムント・ジーマース・アレー 一番地(Edmund-Siemers-Allee 1)
四 スイス・クロイツリンゲン(Kreuzlingen)
五 ボルン広場(Bornplatz)
おわりに
第五章 社会的記憶と個人的記憶の汽水域としての自伝──ルソーにおける抗いのエクリチュール[室井麗子]
一 ルソーによる「社会」への反抗と自伝
二 ルソーが反抗した「社会」とは何か
三 「集合的・社会的記憶」への反抗──ルソーの自伝的著作と抗いのエクリチュール
四 抗いのエクリチュール──諦念と希望
第六章 誰が記憶を語りうるのか──文学研究の観点から記憶叙述の「当事者性」を検証する[三村尚央]
一 「記憶のフィクション」がはらむ困難
二 非当事者による「リアルな表現」とは──北条裕子「美しい顔」
三 原爆の経験を再構築する──アラキ・ヤスサダとカズオ・イシグロ
四 ホロコーストの記憶を継承するとは
五 証言することの困難と「ハイブリッドな証言」、そして叙述の技法としての「聞き書き」
六 記憶を叙述する困難を乗り越えるために──「喪とメランコリー」再考
第七章 記憶の継承をめぐる共同性と公共性の関係──H・アレントにおける「語り口」の問題をてがかりに[田中智輝]
はじめに
一 「語り口」をめぐるアレントとショーレムの論争
二 記憶と責任の継承における共同性と公共性の問題
三 アレントにおける「語り口」の問題
四 公共性の源泉としての私性──むすびにかえて
第八章 「身ぶりとしての抵抗」の習慣形成──鶴見俊輔の戦争体験と反射の自己教育[西本健吾]
一 抵抗の習慣──問題の所在と本章の目的
二 鶴見の戦争体験
三 「反射」の自己教育
四 反射の自己教育における記憶の役割
五 「身ぶりとしての抵抗」としての反射──まとめにかえて
ほか