- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「東北」とは、幕末から近代において作られた言葉である。古代以来の律令制国たる陸奥・出羽二国の領域を「東北」と呼称して、地方の一体性を強調する現象が発生していくのは、主に近代以降のこと。時としてそこには「後進」や「周辺」の意味が込められている場合がある。本書は、この問題関心のもと、近世・近現代の東北史を三つの視点から描写する。一点目は、中央との位置。二点目は、各地との交流。三点目は、中央の影響力のもとでの地域の独自性である。
目次
はじめに/第1講 近世の幕開けと諸藩の成立……兼平賢治/奥羽仕置への抵抗/九戸一揆と奥羽再仕置/朝鮮出兵と「日本のつき合い」/関ヶ原合戦前/関ヶ原合戦と奥羽/江戸開府と奥羽大名/一国一城令/奥羽の馬と鷹/家中騒動と「奥羽の押」/元和飢饉と寛永飢饉/証人制度と奥羽諸藩/直仕置から家老政治へ/殉死の流行/殉死禁止令と剃髪/一七世紀のパラダイムシフト/第2講 藩政の展開と藩主……清水 翔太郎/奥羽諸藩の一八世紀/一八世紀初頭にかけての秋田藩政/享保の改革/銀札仕法事件と藩政の混迷/八代藩主佐竹義敦の時代/佐竹義和と寛政の改革/第3講 社会の変容と諸藩……天野真志/混迷する社会──「内憂外患」との対峙/藩政改革と学問受容/藩校教育と人材登用/遊学と交流/知の広がり/政治関心から政治関与へ/政治動乱への眼差し/第4講 幕末の諸藩と戊辰戦争……栗原 伸一郎/幕末期の奥羽諸藩/幕末政局と奥羽諸藩/諸藩連携と奥羽連合構想/奥羽列藩同盟の成立と活動/列藩同盟と非「奥羽」諸藩/敗戦と「東北」/第5講 明治政府と東北開発……小幡圭祐/〝大久保利通による東北開発〟像/東北開発の嚆矢/大久保利通の意図/東北開発の諸相/大久保利通像の現在/第6講 近代日本の戦争と東北の軍都……中野 良/近代日本の軍隊と軍都/東北における軍都の形成/軍都の拡大/軍都の構造/軍隊誘致運動と存置運動/東北の軍隊の派兵/昭和の戦争と東北の軍隊/戦後の軍都/第7講 戦時体制と東北振興……伊藤大介/東北振興の起こり/東北振興調査会の設置/東北振興第一期総合計画/東北振興の国策会社/国土計画と東北振興/東北振興の終結/戦後の東北振興/第8講 戦前戦後の東北の流通経済──百貨店を中心に……加藤 諭/近代小売業からみる東北の流通経済/連合共進会の動向/東北名産品陳列会、東北産業博覧会と百貨店/中央百貨店の地方進出/戦前における東北の百貨店展開/戦後における東北の百貨店と流通政策/第9講 〔特論〕奥羽の幕領と海運……井上拓巳/統一政権の直轄領と奥羽/陸奥国の幕領/出羽国の幕領/奥羽諸藩の廻米/奥羽城米輸送の開始/河村瑞賢による東廻り航路の城米輸送/瑞賢による西廻り航路の城米輸送/瑞賢による城米輸送の意義/城米輸送の展開/津軽海峡を越える城米輸送/奥羽海運と全国的な海運ネットワーク/第10講 〔特論〕神に祀られた藩主──弘前藩四代藩主 津軽信政……澁谷悠子/信政の生い立ちと人となり/藩主就任と支配機構の整備/シャクシャインの戦いへの派兵/元禄の飢饉での失政/死後の神格化/神に祀られたもう一人の藩主──保科正之/信政治世の特質/第11講 〔特論〕近世後期の災害と復興・防災……高橋陽一/旅が広めた災害情報/家数と米価/豊穣な土地/奥羽開発論へ/復興と温泉/復興・防災社会/災害と観光/第12講 〔特論〕東北開発と地域有力者……徳竹 剛/安積開拓と大槻原開墾/維新期の阿部茂兵衛/大槻原開墾の入植者募集/阿部茂兵衛の意図/開成社の結社/開成社、暗転/安積開拓・疏水事業の人脈/人脈という政治的資源/第13講 〔特論〕近代東北の教育と思想家……手嶋泰伸/旧制中学と新制高校の連続と非連続/東北各県における旧制中学の設立/珍しかった中学校への進学/豪華な教師陣/頻発したストライキ/第14講 〔特論〕東日本大震災と歴史学──史料レスキューの現場から考える……佐藤大介/東日本大震災の経験と歴史学/日本の地域に残る史料(古文書)の危機/自然災害と「史料レスキュー」/宮城での史料レスキュー──災害「後」の救済から災害「前」の保全へ/「もっとも悲しい実証」──東日本大震災で消えた古文書/被災地での史料レスキューの展開/史料レスキューがもたらしたもの──市民ボランティアの動向と意識/歴史を再生する取り組み──地域誌と「大字誌」/被災地との関係が問い直す歴史学・研究者の役割/史料レスキューの可能性──人を結びつけ、人を支援する/地域の歴史に関心を持つ方々へ──宮城被災地からのメッセージ/第15講 〔特論〕東日本大震災と地域社会──福島県双葉郡富岡町の原発立地から全町避難を考える……門馬 健/複合災害と富岡町/大規模災害からの地域性保存/富岡町の誕生と以後の産業構造/『富岡町史』に見る原子力発電所と諸問題/地域資料保全活動から見える富岡町/震災後の町民の受け止め/「地域」でこれからを生きるために/さらに詳しく知るためのブックガイド/編・執筆者一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てん06
qwer0987
アメヲトコ
fseigojp
つわぶき
-
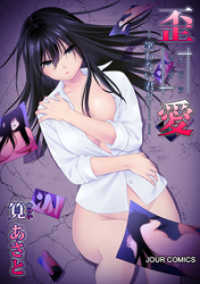
- 電子書籍
- イビツアイ(歪愛)-笑わない君と……-…
-

- 電子書籍
- 日本文学を読む・日本の面影(新潮選書)…
-
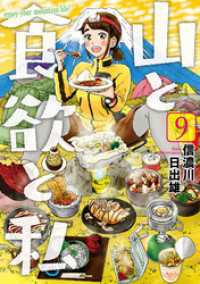
- 電子書籍
- 山と食欲と私 9巻 バンチコミックス
-
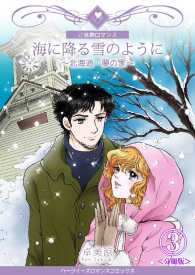
- 電子書籍
- 海に降る雪のように~北海道・夢の家~【…





