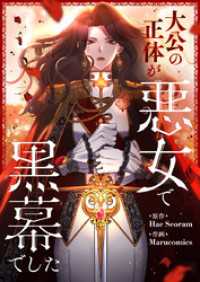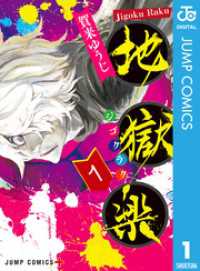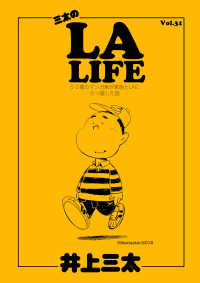内容説明
有害生物との闘いにおける救世主-破壊者は、かくして招かれた。外来の天敵生物をめぐる昆虫学・生態研究の夢、成功と失敗の歴史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
taku
14
当書の大部分は、人間が生活環境を守るために行った生物的防除の思想と歴史変遷を語っている。自然のバランスや生態系の平衡、その実態は期待や願望とは異なることも示す。自然と人間の境界は確かに不明瞭だけど、線引きするまでもない。様々な生態系に、人為的影響を及ぼさずに暮らせないのだから。外来生物の移入と従来環境への多大な影響。著者自身の活動も通じ、過去の失敗を経験知として、これからの有効策として何をすべきかで締め括る構成が鮮やか。新たな知見を得られた。2024/06/04
FOTD
13
『歌うカタツムリ』の著者による、人と自然との関係の歴史。ここには、外来種から固有の在来種をどのように守ってきたが記されている。薬品を使用する「化学的防除」と外来種の天敵を導入して駆除するという「生物的防除」。レイチェル・カーソン『沈黙の春』で「化学的防除」では生物が姿を消してしまうことがわかり「生物的防除」が良い方法と思われていたが必ずしも成功するものではないという。著者は小笠原諸島の父島で、外来種のウズムシにより危機的状況にある在来カタツムリの保護に関わっている。私たちにできることはないだろうか。2024/02/19
kamekichi29
6
害虫駆除の歴史と天敵を用いた駆除の功罪。世界中から天敵を見つけてきて、導入していたようで、驚いた。 最後は、著者が関わった小笠原での駆除の記録。2025/02/06
belier
4
「招かれた天敵」とは有害な外来生物退治に導入された生物のこと。化学物質ではない生物防除であれば問題ないかといえばとんでもない。天敵が思わぬ害を及ぼしてしまうこともある。何がよくて何が悪いか、生物の世界も一筋縄ではいかない。研究者たちの苦闘の歴史が語られている。生物のことに限らず、社会のあらゆる活動の教訓となるようなストーリーが多く、戦記物で意思決定を学ぶような読み方ができると思った。とはいえ苦い教訓だけでなく、ウチワサボテンなどのホラーのような展開や、来日した研究者の心温まる話もあり、純粋に楽しく読めた。2023/10/25
たかぴ
4
人間の手による意図せざる、或いは人為的な自然環境の変化。それは外から生物を持ち込んでしまうというありふれた事から始まり、取り返しのつかない程、自然環境にダメージを与えてしまう。その対策をする事で更なる悪循環も生まれる事もあるし、後から見ると只の僥倖で回復する事も。 多様性を持った対処法を持っていないと、悪化した時に引き返せない。2023/06/17