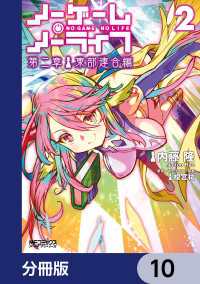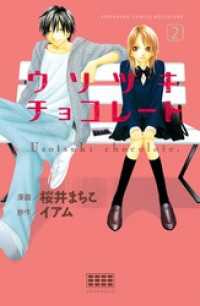- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本の村々は、長い歴史のなかで工夫に工夫を重ね、それぞれの風土に根ざした独自の生活パターンと人づきあいのあり方をかたちづくってきた。そのしくみや特徴をつぶさに観察してみると、村を閉鎖的で前近代的なものとみなすステレオタイプこそ、むしろ古びたものにみえてくる。コミュニティの危機が叫ばれる今日、その伝統を見つめなおすことは私たちに多くの示唆を与えてくれるのだ。日本の村に息づくさまざまな工夫をたどり、そのコミュニティの知恵を未来に活かす必読書。
目次
はしがき/第1章 村の知恵とコミュニティ/1 村の知恵/人間関係に迷う/知恵の発光体/コミュニティとは/2 コミュニティの構造/なわばりの否定/なわばりと居場所/他者への配慮となわばり/孤立化とあたたかみ/コミュニティの典型としての村/第2章 村とローカル・ルール/1 村とは何か/ふたつの村/地域経営としての村/2 ローカル・ルール/住民を強制すること/つとめ/作法という名のローカル・ルール/3 生活組織としてのコミュニティ/町内会/小学校区のコミュニティ/第3章 村のしくみ/1 村のタテの構造と関係/家格と年齢/目上・目下の判断/親分・子分/庇護と奉仕/2 村のヨコの関係/現実と幻想と/技と作法/ヨコの関係の強い村落構造/信仰的な講の裏のはたらき/3 人間と自然/採取から開墾へ/人間参加型自然/山が荒れる/肥料/村の空間的構成/村の山と水/自然と争わない/4 村での仕事と権利/トレードオフと話し合いの重要性/リーダーを悪者にしてもよい理由/村の生活維持/共同労働と共同占有/個的役割とリーダーシップ/文化型リーダー/利用権に対する配慮/フェイス・トゥ・フェイスの現場/第4章 村のはたらき/1 交換不可能性とエゴイズム/交換不可能性/エゴイズムを抑える/2 弱者救済/家族における弱者救済/三世代家族の長所/やわらかい三世代家族/村における弱者救済/弱者/に与える特権/子どもたちも働く/3 災害対応/地震への対応/村での水害/火事──許されない失敗/4 村の教育──平凡教育/平凡教育と非凡教育/カツオの変身/知恵としての平凡教育/学力とは/第5章 村における人間関係/1 あいさつ/簡便なコミュニケーションの手段/あいさつの型/呼びかけ/2 不公平を嫌う/損をしない/「不公平」という切り札/3 話し合いと意思決定/意思決定のかたち/寄り合い/全員一致制/第6章 村の評価と村の思想/1 村の意図的消滅論/個人の自由を束縛する/近代文学における個の自立論/2 村の自然消滅論/近代化のプロセスとして/民主主義と権威主義/村と資本主義的生産/近代技術のプラス・マイナス/過疎化の危機/3 Society 5.0と異なる方向へ/Society 5.0とは何か/自然を活かしたつきあい/当たり前の平たい人間関係/自由主義と共和主義/反君主制としての共和主義/村は共和主義か?/村の知恵を活かす/あとがき/注/参考文献