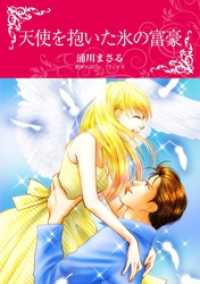内容説明
●大谷竹次郎、城戸四郎、永田雅一、堀久作、小林一三――経営者たちの興亡を中心に描く映画「経営」史
●日本映画120年、映画の舞台裏は、かくも個性的な経営者たちの「世襲」をめぐるバトルロイヤルだった
●三船敏郎、石原裕次郎、勝新太郎、中村錦之助、そして黒澤明も、あくまで経営者として登場
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yamatoshiuruhashi
55
タイトル通り。活動写真伝来以来、日本の映画会社の栄枯盛衰をそれぞれの社長の活躍、暗躍、権謀術数を通じて描いたもの。そこに昭和期に入ると三船敏郎、石原裕次郎らの大スターあるいは黒澤明などの名匠たちのプロダクションが絡んでくる。が、結局、映画は興行であり、そこには裏社会が絡んでいることも拭い去ることができない、どころか表裏一体とも言えるほどの状況であることがよくわかる。右翼も左翼もヤクザもなんでもありの業界は読み物としてそれなりに面白いが、映画ファンとしては触れたくない部分多々あり。2023/03/06
d3
38
映画は作品や監督、俳優、脚本家を軸に語られることが多いが、本書では経営の視点から映画産業の成り立ちをあきらかにしていく珍しい試みに挑んでいる。 映画は総合芸術と称される。ところが読み進めていくと、文学や絵画、音楽とは性質が違うものであることが理解できるだろう。 約100年前に映写機が発明されたそのときから、映画とは”すべてが興行ありき”なのだ。 映画史を俯瞰すると見えてくるのは「良い映画を作れば客は観に来る」と信じた製作者たちが、業界から退場を余儀なくされる残酷な事実の繰り返しである。2023/06/09
ぐうぐう
37
冒頭にこんな場面がある。1889年、歌舞伎座開場公演で九代目市川團十郎を観る16歳の小林一三、のちの阪急創業者がいて、翌年の京都祇園館で同じく團十郎を観る双子の兄妹・松次郎と竹次郎がいるが、二人は松竹の創業者となる。この逸話は中川右介が自著『松竹と東宝』でも取り上げているが、本書で改めて語られるのには意味がある。日本の映画黎明期に歌舞伎が果たした役割が強いからだ。とはいえ、本書は役者達からではなく、タイトルにあるように経営者の視点から描かれる映画史だ。(つづく)2023/06/14
nishiyan
13
映画伝来から1971年の松竹、東宝、大映、東映、日活による五社体制崩壊までを経営者の視点から描いた映画史。戦後の復興期から日本映画全盛期に突入すると、映画製作に情熱を捧げ続けた者、映画製作は部下に任せ、ホテルなど他の事業拡大に勤しむ者と経営者の個性がその後の会社の命運を左右する様はまさに悲喜劇のようである。いわゆる五社協定と対立した石原裕次郎、三船敏郎らのスタープロの時代は長続きせず、日本映画衰退期のあだ花のようであり、彼らがテレビへ行くしかなかったのも読みごたえがあった。2023/02/25
コリエル
6
大変な労作。日本映画の成り立ちから、最盛期と凋落を描き出してある。宝塚歌劇と東宝の関係すら知らなかったにわか者には新しい情報ばかりでとても楽しめた。日本映画を成立させた映画会社五社の社長たちは、小屋主のようなところからスタートしているせいか創業者や中興の祖が権力を握り続けていつしか動脈硬化を起こし、勝手に自爆していったという印象が強かった。中でもやはりエンターテイメントの要点としては、客あってのもの種であり大衆が何を欲しているのかを見極める目と理性ということだろうか。2023/07/02