内容説明
日本人の数学アレルギーはきわめて深刻である。本書は博覧強記で知られる筆者が、古今東西の逸話を交えつつ、数式を使わずに面白く数学の本質を解説する。
目次
はじめに
Chapter1 数学の論理の源泉──古代宗教から生まれた数学の論理
Chapter2 数学は何のために学ぶのか──論理とは神への論争の技術なり
Chapter3 数学と近代資本主義──数学の論理から資本主義は育った
Chapter4 証明の技術──背理法・帰納法・必要十分条件・対偶の徹底解明
Chapter5 数学と経済学──経済理論を貫く数学の論理
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KF
14
流し読みしてわかるものではないですね。時間をかけてしっかり読まないと得るものは乏しいです。何となく「そんなものなのかなぁ」とぼんやり持っていかれてしまう感じですね。 考え方として「数学」を用いて経済学を語っているのでしょうが、「現実は異なる」という例も説明しています。資本主義経済体制化で自由競争で…何故か経済が上を向かない。この場合の下手人は賃金率が下がらない点にありました。レッセフェールと成り得ていない。近代以前の日本経済は資本家個人の運営ではなく番頭の合議運営というのも面白かった。 結局面白かったね。2024/01/26
九曜紋
11
再読本。2001年刊。数学の本というよりは論理学の本というほうが正確か。論理学の考察が数学を通して結局のところ経済学に収斂していく。学生時代、一般教養で経済学を選択したのだが、古典派経済学史をダラダラ喋るだけでひどくつまらなかったので、この本のような講義が聴きたかった、と思った。必要条件と十分条件、対偶など、普段、学術書を読む際にも有益な概念を再確認できたことは収穫だった。2020/08/05
りょうみや
8
一見、数学の本に見えないがやっぱり数学の本。経済の入門としてもよい。宗教、法学、国民性、歴史、資本主義などに数学の論理性を絡めた展開はとても新鮮であった。数学が本当に身についているとは著者のような人なのだと思う。数学だけでなく幅広い教養の重要さを再確認する。数学、経済のみならず、著者の歴史や文学における教養の深さには感嘆させられる。著者の本は初。これから続けて読んでいきたい。あと、本書は数学嫌いよりも数学好きがますます数学好きになる本かもしれない。2016/11/19
さきん
7
数学の勉強に苦しんでいた時に、この本にであった。苦手な数式が少なく、私のもっとも知りたかった数学の存在意義や捉え方を教えてくれた。さらに小室直樹先生をはじめて知った。2015/07/05
popcorn
7
再読です。数学の本質は論理であり、何も難しく考える必要はないと数学の世界へ誘う内容となっています。数学の効用が形式論理学(同一律・矛盾律・排中律)を軸に様々な例を挙げながら解り易く説明されており、確かに数学が嫌いでも苦手でも充分に理解できます。この本と併せて『論理の方法』を読めば、論理的に思考するということがどういうことなのかがはっきり解り、頭の中をかなり整理することができるのではないかと思います。数学に苦手意識を持つ人(私も含みます)にとってありがたい本ですが、理系の人が読んでも有益だと思います。2013/11/30
-

- 電子書籍
- なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?【…
-
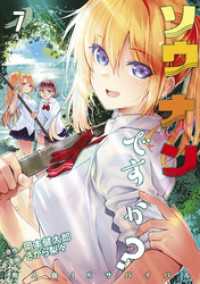
- 電子書籍
- ソウナンですか?(7)






