内容説明
難事業に立ち向かった叩き上げの天才――
老中・松平信綱は何故「知恵伊豆」と称されたか?
明暦3年(1657)1月、江戸が燃え尽きた――。のちに言う「明暦の大火」である。日本史上最大、世界史的に見ても有数の焼失面積と死者数を出したこの大惨事に立ち上がった男がいた。代官の息子に生まれながら、先代将軍・家光の小姓から立身出世を遂げた老中・松平伊豆守信綱。その切れ者ぶりから「知恵伊豆」と呼ばれた信綱は、町奴の長兵衛を「斥候」として使いながら、「江戸一新」に乗り出した。現在の東京に繋がる大都市・大江戸への「建て替え」が始まったのだ。
読売新聞連載「知恵出づ 江戸再建の人」より改題。
目 次
第一章 大火発生
第二章 復興開始
第三章 米の値段
第四章 復興景気
第五章 抗 争
第六章 大移動
第七章 討ち入り
第八章 遷 都
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
230
門井 慶喜は、新作中心に読んでいる作家です。本書で、老中・松平伊豆守信綱を初めて知りました。「明暦の大火」復興で思い切った都市再開発を行なったので、江戸の街の寿命が延びたんでしょうね。やはり危機的な時代には、天才が登場します。 https://www.chuko.co.jp/tanko/2022/12/005609.html2023/01/23
パトラッシュ
161
「知恵出づ」とまで呼ばれた老中松平信綱が、明暦の大火で焼失した江戸の再建に辣腕を振るう物語かと思うとあてが外れる。江戸城の再建方針は保科正之や酒井忠清の主張を容認し、新たな街への建て替えでも自らは下情を知らぬと言い、幡随院長兵衛や水野十郎左衛門の意見を受けて決めていく。信綱の知恵とは己の足らぬところを知り、将軍と幕府への奉公に専心して傲慢に陥らず、広く考えを徴して大方針を決定するところにあった。そんな信綱を誰もが信頼したため、江戸は拡大と復興へ舵を切った。危機の指導者はどうあるべきかとの理想像を提示する。2023/02/20
とん大西
129
江戸一新。古地図を片手に現代の地図と見比べながら読んだら、愉しさも倍増したかもしれません。まぁ、ザックリの23区脳内ナビでも十分に趣を感じられた松平信綱のまちづくり。時代は武断から文治、一つの分岐点。そんな時に起こった明暦の大火。江戸の街を焼きつくす大災害にうちひしがれる町民、困惑する幕閣。求められたからこそか、知恵伊豆。円熟味と斬新さが織り成す行政改革都市改革。伸び代が存分にあった「まち」、安息を求める民、真摯で柔軟な宰相。全てが融合しての江戸一新。趣がありましたね。2023/04/23
のぶ
115
江戸時代初期に起きた明暦の大火が話の起点となり、大半の部分を焼失した江戸の町を復興させるために命を受け立ち上がった男の物語である。門井さんは今までに「家康、江戸を建てる」や「東京、はじまる」のようなプロジェクト物を残しているので、その延長かと思ったが、物語は再興を託された老中・松平伊豆守信綱の人物像に重きが置かれていた。その仕事ぶりは想像を絶するほどの大胆さで、あの時代にこれだけのアイディアが浮かんでいたものだと驚いた。松平信綱は初めて知ったが、それだけ明晰な人物であることが分かって良かった。2023/01/21
いたろう
86
「家康、江戸を建てる」で、何もない寒村から江戸へのまちづくりを描いた門井さんの今作は、江戸の再開発、大拡大の物語。若い将軍、4代家綱の治世、江戸城の天守まで焼け落ちた明暦の大火の後、いかにして火事が拡がらない街を作るかが大きな課題となる。そこで計画されたのは、密集している狭い江戸の街の拡大。それを進めたのは、「ちえいづ」と呼ばれた、老中・松平伊豆守信綱らだが、それだけでなく、いろいろなひとの力で江戸の街が郊外に拡大していき、侍の街だった江戸が、侍と町人の街である「大江戸」になっていくのが、とても興味深い。2023/02/16
-
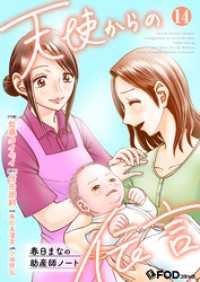
- 電子書籍
- 天使からの伝言-春日まなの助産師ノート…
-

- 電子書籍
- 猫と紳士のティールーム 2巻【特典イラ…
-

- 電子書籍
- そもそもウチには芝生がない 分冊版 1…
-
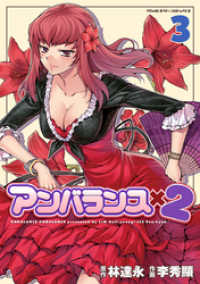
- 電子書籍
- アンバランス×2 3 ヴァルキリーコミ…
-
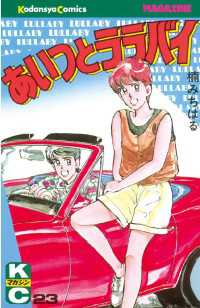
- 電子書籍
- あいつとララバイ(23)




