内容説明
日本各地の民芸館・有名店を旅しながら、民藝の世界を紹介する本。
日本民藝館からはじまって益子、盛岡、会津、松本、南砺、京都、丹波、
倉敷、出雲、八女、読谷……など各地域の代表的な手仕事を紹介します。
各スポットでは、民藝品の特徴や歴史を紹介。
さらに柳宗悦や濱田庄司、芹沢ケイ介、丸山太郎、
河井寛次郎、吉田璋也、バーナード・リーチ、外村吉之介などの
民藝同人のゆかりを解説しています。
旅で役立つガイドとして使うのはもちろん、
民藝の入門書としても楽しめます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ann
37
自分にとって民藝といえば浅川巧である。リーチよりも宗悦よりも。そして現代ならば過日逝去された久野恵一氏である。先日伺った東長崎の小鹿田焼ソノモノ、20年前に緊張しながら恐る恐る訪れた松本民芸館、ちきりや工芸店。山陰地方と倉敷美観地区は今すぐ飛んで行きたいくらい。益子でさえ今は遠い、、、2021/12/04
かおりんご
29
伝統工芸品と民藝の区別って難しいなと思いながら読む。民藝と名付けられたときはそんなに値がはるようなものじゃなかったかもしれないけれど、今じゃ気軽に手の出せないものもある。この本は、民藝を扱っている美術館やお店を紹介。益子は、また今度ゆっくり行きたい。2020/10/30
ふう
14
全国60か所以上の民藝館。片っ端からデジタル地図に印していたが、キリがない。この本は買うしかない。紹介された関西の美術館や民藝店には半数以上行ったことがあるが、後は益子と沖縄の数か所しか知らない。心ゆくまで民藝(と温泉とお酒をちょっとだけ)の旅がしたい。2022/02/13
らびぞう
8
TVで井浦新さんがナレーターをすると言う「民藝の100年」を見て、興味を持った。「民芸」は観光地のお土産売り場で、この文字は見たことがあるが、「民藝」は、私の今までの人生の中で、あまり見慣れない言葉だ。そうして、そこから、この「民藝」を広めた人物が柳宗悦だ。大衆的でありながらも、そこには、素朴な美がある。全国に散らばっていた、それらを集め、系統つけたことにより、今、現在の私たちにも、それらが色褪せることなく、継承されているものを見ることが出来ることとなった。小鹿田焼のピッチャーが特に気になった。2022/03/17
アズル
8
図書館本。民藝館や工芸館、窯元、店舗などのガイドブック的な一冊。柳宗悦らの「民藝運動」については、サクッと紹介。民藝の品々を実際に購入できる店舗に行きたいです。2021/03/16
-

- 電子書籍
- 一日1回俺の理性が負けるとき15 ヤン…
-
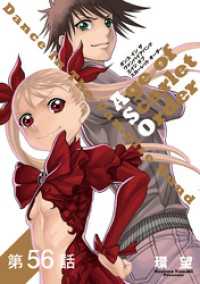
- 電子書籍
- 【単話版】ダンス イン ザ ヴァンパイ…
-
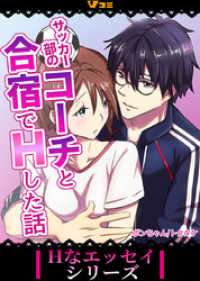
- 電子書籍
- サッカー部のコーチと合宿でHした話4 …
-

- 電子書籍
- 新版 広報・PRの基本 この1冊ですべ…





