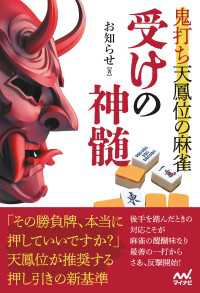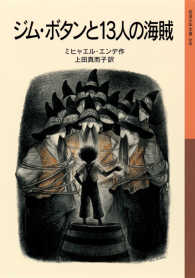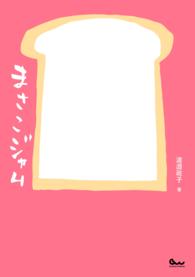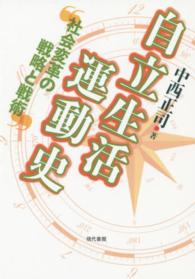内容説明
70年代後半から80年代にかけ、世界を股にかけ、未知の生物や未踏の秘境を求めた男たち。それが川口浩探検隊。ヤラセだとのそしりを受け、一笑に付されることもあったこの番組の「真実」を捜し求めるノンフィクション。当時の隊員たちは、どのような信念で制作し、視聴者である我々はこの番組をどのように解釈してきたのか。そして、ヤラセとは何か、演出とは何か。当事者の証言から、テレビの本質にまで踏み込む危険な探検録。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
203
ヤラセ番組として名高い『川口浩探検隊』。モンド映画の様な海外習俗誤解番組だが、怪物や原人など各回様々なギミックを用意してファンも多かった。ヤラセと気づきながら楽しんでいた大らかな時代だった。この番組に情熱を燃やした男たちの闘いの記録。ヤラセとはいえロケには危険が付き纏い、カメラには映らなかった苦労があった。当時の現場は完全なブラックで、死んでもおかしくない事故もあった様だ。むしろ裏話の方が面白いのか。歌で有名な、ピラニアにかまれた川口浩はヤラセではなかった。撮影後、撤収時のアクシデントだった。2023/09/13
☆よいこ
107
ドキュメンタリー。1977年から1985年まで放送されたテレビ番組「水曜スペシャル」の制作現場を、当時のディレクターや関係者を探し出し取材する。川口浩探検隊の過剰演出はどう作られたのか?1984年の「ロス疑惑」ワイドショーのヤラセ問題、旧石器発掘偽造事件など、テレビ制作の裏事情を探る▽「ドキュメンタリーじゃないんだよ、エンタメだからね」視聴率主義な時代で面白ければコンプラ気にしない世界だったテレビ業界は、現代から見れば異世界みたいだ。ワクワクしてテレビにかじりついていた頃を懐かしみつつ読了。2023/10/01
ma-bo
102
水曜スペシャル「川口浩探検シリーズ」。巻末の年表を見ると私が4歳から12歳の間に放送されていた。後期はある程度見ていたはずだけど意外と記憶には残ってないなぁ。当時の関係者や出演者への取材で番組の作られ方、演出の仕方、舞台裏。今だからこそ話してくれる内容が満載。そこから他番組(アフタヌーンショー)のヤラセや三浦和義事件、徳川埋蔵金まで出てくる。「テレビとの付き合い方は半信半疑という精神状態である。信オンリーになると妄信となるだけだ。かといって不信だけだと味気ない。半信半疑が最もワクワク出来る立ち位置だ。」2023/07/01
へくとぱすかる
87
こうして昔日の「探検隊」と比べてみると、テレビはものすごく変わったという思いがする。メディアとしてのテレビは、まず見せるものであったからこそ、カメラがとらえる映像のために情熱をかたむけ、肉体労働の手間も時間もかけたのだろう。ヤラセ・演出という単語ひとつで語れない複雑さがあったし、受け取る視聴者と製作側との思いのずれもあったことがわかる。今でもテレビのドキュメンタリーにはおもしろいものがあるけど、それはやはりこの世界のちがった場所や角度を見せてくれて、室内のスタジオの中で完結していないからではないかと。2023/01/28
R
81
序盤は「川口探検隊」というコンテンツの紹介と熱い思いをないまぜにして、楽し気に語る内容だが、後半になるに従い、ヤラセとは、テレビとはといったものに踏み込んでいて、総じてこの本のつくり、展開そのものが「川口探検隊」的になってて面白かった。いかにもな昭和のテレビマンなる怪人を追っていたり、当事者たちの謎の証言が集まったり、演出が見事で、ヤラセとヤリ、ありそうとあるの違いについてとか、そもそも論を存在するかわからない昭和のテレビマンに語らせて終わるというのが実によかった。2023/11/04