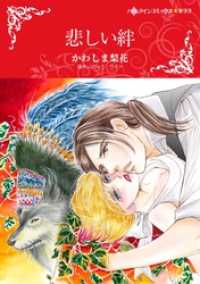内容説明
近年、日本政治においても、「右」と「左」ではなく、「保守」と「リベラル」という対立図式が語られることが多くなった。しかし、混乱した言論状況のなか、保守とは何か、あるいはリベラルとは何か、という共通理解があるとは言えない。本書は、欧米の政治思想史を参照しつつ、近現代の日本に保守とリベラル、それぞれの系譜を辿り、読み解く試みである。福沢諭吉、伊藤博文以来の知的営為を未来につなげ、真の「自由」を考える。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よしたけ
57
日本政治を近代偉人思考と読み解く。保守主義は「培われた制度や慣習を重視し、歴史的に形成された自由を発展させ秩序ある漸進的改革を目指す思想や政治運動」だが、日本は明治以来「追いつき型近代化」を目指し欧米制度や文物を導入後、経済成長後に経済成長に代わる目標や歴史的価値を見出せず、保守あるべき姿に成り立たなかったため、今後は価値観洗出しが最重要と説く。なお欧州では小政府説くリベラリズムが保守、政府の積極役割重視のリベラリズムがリベラルだが、米は封建的伝統と無縁のため欧州リベラルよりも左派的色彩が強い、という。2023/08/11
Sam
47
昨今「リベラルとは何か」という問いをよく目にするが、本書はその普遍的な概念を論じるというよりは「自らが社会を担っているという自負・責任感を持った”保守”と、多様な価値観を表明し受け入れるだけの気概と道理を持った”リベラル”の確立」を目指すべきという立場から日本固有の保守とリベラルについて論じたもの。「反共と経済成長以外に共通の価値観を持たない巨大な保守政党が長く統治の役割を担った」日本の政治の歴史や特殊性をよく理解することができた。編集もの特有の冗長さはあるが良書と思う。2023/04/21
ふみあき
41
各種媒体で発表された数本の論考が収録されており、多少論旨が重複する箇所もあるが、書き下ろしも3篇収録。ただ『保守主義とは何か』(中公新書)の第4章が(ほとんど)まるまる再録されている。丸山眞男の主体論についての第5章が少し抽象度が高いくらいで、全体的に文体は平易。短いものの福田恆存も論じられており、「人間は再びコスモスの一部であることに歓喜すべき」なんて、今こそ傾聴に値する言葉か。「個人の自由を重視するあまり、一国の安全保障に無関心」なのはリベラルの本懐ではないと著者は言うが、そういうリベラルは実に多い。2023/01/17
Tomoichi
31
著者の「保守主義とは何か」が面白かったので購入。本書も当たりで、色々と自分なりに保守主義とは何かを考える機会になった。短い文章で本書の説明は難しいが、近現代の政治思想を学べる一冊です。2025/02/09
confusion_regret_temptation
30
6章7章終章が読みどころ。ここのために序章から5章があった。保守、リベラルと画一的に区切っているが定義づけは果てしなく難しく、日本においては今なお保守もリベラルも存在しえてはいないことをじっくり解説しています。とても興味深い本でした。2023/04/25