内容説明
「カテーの問題」と言われたら、その「カテー」が家庭か假定かあるいは課程か、
日本人は文脈から瞬時に判断する。
無意識のうちに該当する漢字を思い浮かべながら……。
あたりまえのようでいて、これはじつに奇妙なことなのだ。
本来、言語の実体は音声である。
しかるに日本語では文字が言語の実体であり、
漢字に結びつけないと意味が確定しない。
では、なぜこのような顛倒が生じたのか?
漢字と日本語の歴史をたどりながら、その謎を解き明かす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
73
元々外国人向けの日本語の漢字についての文を膨らました本だという。砕けた講義調の新書。日本語は文字として漢字を取り入れることで、それに引きずられるいびつな発展をしてしまったと著者。同音異義語の多さから、頭の中で文を参照しながら会話をするという世界でも珍しい言語であるなど、一種の日本人論。明治期と終戦時の漢字撤廃論の流れなど政府の日本語政策の話が興味深かった。かな文字論者やローマ字論者などそういう連中がいたなあと再認識。中国由来と日本発の漢字やそれらの組み合わせなど細かく考察してあり、興味がある人にはお勧め。2018/04/09
takaC
73
ずいぶんこむずかしいというかややこしい内容で、まじめに読んだらえらく疲れて、最後まで読み切れてホッとした。2016/11/26
ネギっ子gen
69
【日本語には、相互に無関係だが偶然に同じ音を持つことばが、何千も何万もある】のに混乱しないのは、“ことばの背後に漢字がはりついている”からと、『お言葉ですが…』で知られる著者が、“漢字の謎”を追った書。平成13年刊。<漢字と日本語とはあまりにも性質がちがうためにどうしてもしっくりしないのであるが、しかしこれでやってきたのであるからこれでやってゆくよりほかない/よって立つところは過去の日本しかないのだから、それが優秀であろうと不憫であろうと、とにかく過去の日本との通路を絶つようなことをしてはいけない>と。⇒2025/08/07
ばりぼー
43
日本語というのは、地球上どこにも親戚のいない、孤立無「縁」のことばである。その日本語が中国から漢字を輸入し、漢字を用いて表記することになったのは、恩恵を受けたと考えるのは間違いで、日本語にとっては不幸なことであった。日本語が漢語の浸食を受けなければ、「理」や「義」や「徳」に相当するような、しかしそれらとは違った日本人の抽象概念が生活の中からうまれ、またそれらをさすことばがうまれていたであろうが、その可能性が断たれたのである…。私も日本人は合理的に漢字を取り込んだと思い込んでいたので、目から鱗でした。2016/09/20
ひろき@巨人の肩
43
図書館本。言語学として日本語を学べる必読本。漢語と漢字の完全な調和に驚き、その漢字が日本語で使うのに如何に難しいか論理的に理解できた。隋・唐の時代の漢語の大量輸入、明治維新の西洋語の大量輸入によって起こる日本語変質の歴史も興味深い。その中で漢字の訓読みに隠れる生粋の日本語は昔から話されていたと思うとロマンを感じる。口元が不器用な日本人が、日本語が成熟する前に漢字を取り入れてしまい、西洋語の字音語化することで、脳で漢字変換しながら日本語を聞くという特殊能力を身につけた。そんな不器用な日本人が愛おしくなる。2016/05/19
-
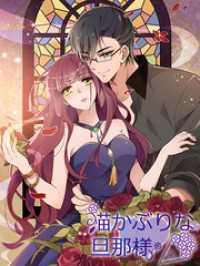
- 電子書籍
- 猫かぶりな旦那様 第32話 秘密の水遊…
-

- 電子書籍
- 財政担当のためのはじめての予算査定Q&A
-
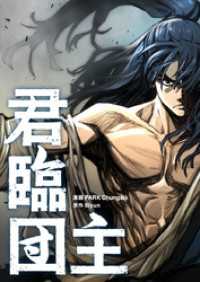
- 電子書籍
- 君臨団主【タテヨミ】第19話 picc…
-
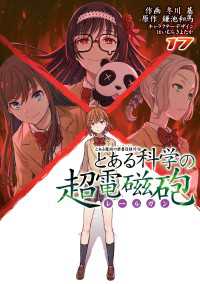
- 電子書籍
- とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の…
-
![[現代語訳]ベスト・オブ・渋沢栄一](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0976948.jpg)
- 電子書籍
- [現代語訳]ベスト・オブ・渋沢栄一




