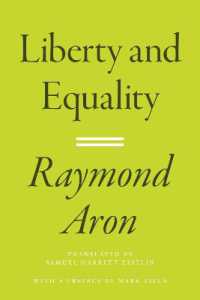内容説明
後ろに誰かいる気がする、何か音が聞こえる、誰もいないはずなのに気配を感じる……。
妖怪は水木しげるによって視覚化され、いまではキャラクターとしていろいろなメディアで流通している。他方、夜道で背後に覚える違和感のように、聴覚や触覚、嗅覚などの感覚に作用する妖怪はあまり注目されてこなかった。
日本や台湾の説話や伝承、口承文芸、「恐い話」をひもとき、耳や鼻、感触、気配などによって立ち現れる原初的で不定形な妖怪を浮き彫りにする。ビジュアル化される前の妖怪から闇への恐怖を思い出すことで、私たちの詩的想像力を取り戻す。
目次
序 妖怪の詩的想像力
1 ビシャガツクに遭った夜
2 妖怪感覚と命名技術
3 五官に感じる妖怪
4 名辞以前の恐怖
第1章 花子さんの声、ザシキワラシの足音
1 見えない花子とザシキワラシ
2 闇に這い回るもの
3 「聴覚優位の時代」の妖怪
第2章 文字なき郷の妖怪たち
1 烏来(ルビ:ウーライ)古老聞き書き
2 言葉を奪うウトゥフ
3 魂のゆくえ
第3章 「化物問答」の文字妖怪
1 「しろうるり」と「ふるやのもり」
2 「文字尊重の時代」の妖怪たち
3 妖怪と識字神話
第4章 口承妖怪ダンジュウロウ
1 話された妖怪
2 ダンジュウロウと団十郎
3 「伝統」の発見と妖怪
第5章 狐は人を化かしたか
1 「迷わし神型」の妖狐譚
2 狐狸狢、冤罪説
3 妖怪体験と解釈のレベル
第6章 台湾の妖怪「モシナ」の話
1 「お前さんはモシナかい?」
2 モシナの事件簿
3 「鬼」化するモシナ
第7章 東アジアの小鬼たち
1 お人よしの水鬼
2 『台湾風俗誌』の鬼神たちと、沖縄のキジムナー
3 韓国人アイデンティティーとトケビ
第8章 「妖怪図鑑」談義
1 ある妖怪絵師の死
2 水木少年はベトベトさんに遭ったか
3 妖怪図鑑の思想――『琉球妖怪大図鑑』
第9章 妖怪が生まれる島
1 台湾「妖怪村」探訪記
2 赤い服の女の子は、なぜいない?――『台湾妖怪図鑑』
3 台湾の妖怪学――『妖怪台湾』
初出・関連論文、随筆一覧
あとがき――天狗に遭った先祖
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
へくとぱすかる
アナクマ
アカツキ
円盤人
-
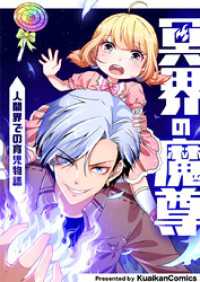
- 電子書籍
- 冥界の魔尊~人間界での育児物語~【タテ…
-
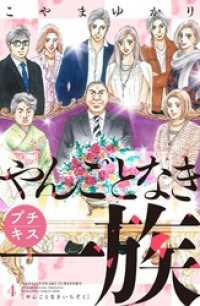
- 電子書籍
- やんごとなき一族 プチキス(4)