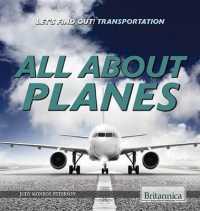内容説明
カリブー、ワタリガラス、クマ、ビーバー、ギンザケ、オーロラ ……
多種とともに生きのびる知恵を知る
人類学の冒険がはじまる
内陸アラスカではかつて「犬に話しかけてはいけない」という禁忌があった――。
本書は、マルチスピーシーズ民族誌と環境人文学の視点から、フィールドワークを通してアラスカ先住民の人々と「自然環境」との関わりを描く。
内陸アラスカ先住民の人々は、動植物や精霊、土地との関係性のなかで息をひそめながら暮らしてきた。「人間」が問い直されている今、彼らの「交感しすぎない」という知恵から「自然との共生」を再考する。
目次
はじめに――ある日の野帳から
第1章 マルチスピーシーズ民族誌へようこそ
現代人類学への道
マルチスピーシーズ民族誌の誕生
人新世と環境人文学――マルチスピーシーズ民族誌との関連から
第2章 ニコライ村への道のり
ニコライ村
フィールドワークの始まり
本書のおもな登場人物
個人主義的な人々?
徒弟的なフィールドワーク
フィールドワークの身体性
第3章 ワタリガラスのいかもの食い──ある神話モチーフを考える
トリックスターとしてのワタリガラス
神話は子育てによく効く?
犬の屠畜とワタリガラス神話
犬屠畜モチーフが他地域からもたらされた可能性はあるか?
〈ワタリガラス〉の犬肉食は、動物行動学で説明できるか?
〈ワタリガラス〉の犬肉嗜好モチーフは修辞戦略としてみなしうるか?
多種の因縁を語る神話
第4章 犬に話しかけてはいけない──禁忌から考える人間と動物の距離
ある禁忌の語りから
運搬・護衛・狩猟
犬ぞりの受容と二〇世紀初頭の変化
犬ぞりの現在
犬―人間のハビトゥス
第5章 ビーバーとともに川をつくる──「多種を真剣に受け取ること」を目指して
ビーバー論争
生態学・生物学と対話するマルチスピーシーズ民族誌
ビーバーとディチナニクの人々の関わり
ビーバーダムとギンザケ
ビーバー擁護派と反対派の二項対立を超えて
キーストーン種とともに考える
マルチスピーシーズ民族誌が目指すこと
第6章 「残り鳥」とともに生きる──ドムス・シェアリングとドメスティケーション
ドメスティケーションの周辺から考える
野鳥の餌づけ・保護・飼育
「残り鳥」と住まう
野鳥とのドムス・シェアリング
ドムス・シェアリングとドメスティケーション
第7章 カリブーの毛には青い炎がある──デネの共異身体をめぐって
北方アサバスカンの身体
共異体と社会身体
サイボーグ・インディアン
カリブーの民とオーロラ
巨大動物と超自我
ぬくもりの共異身体
第8章 コウモリの身内──環境文学と人類学から「交感」を考える
悪魔からロールモデルへ
目的としての「交感」と実用的な「交感」
生きものとの会話と非会話
「交感しすぎない」という知恵
おわりに――内陸アラスカ先住民の知恵とは何か?
マルチスピーシーズ民族誌の射程
各章の概要
アラスカ先住民の知恵
第三の道を探る
あとがき
注
初出一覧
図版一覧
動物の名称一覧
参考文献一覧
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ポテンヒット
owlsoul
たかぴ
;
中桐 伴行
-

- 電子書籍
- 魔法が使えない悪役令嬢に転生しました【…
-
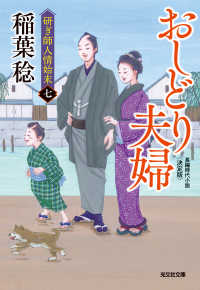
- 電子書籍
- おしどり夫婦 決定版~研ぎ師人情始末(…