内容説明
大東亜共栄圏とは、第2次世界大戦下、日本を盟主とし、アジアの統合をめざす国策だった。それはドイツ・イタリアと連動し世界分割を目論むものでもあった。日本は「自存自衛」を掲げ、石油、鉱業、コメ、棉花などの生産を占領地に割り振り、政官財が連携し、企業を進出させる。だが戦局悪化後、「アジア解放」をスローガンとし、各地域の代表を招く大東亜会議を開催するなど変容し、迷走する。本書は、立案、実行から破綻までの全貌を描く。
目次
序 章 総力戦と帝国日本―貧弱な資源と経済力のなかで
第1章 構想までの道程―アジア・太平洋戦争開戦まで
第2章 大東亜建設審議会―自給圏構想の立案
第3章 自給圏構想の始動―初期軍政から大東亜省設置へ
第4章 大東亜共同宣言と自主独立―戦局悪化の1943年
第5章 共栄圏運営の現実―期待のフィリピン、北支での挫折
第6章 帝国日本の瓦解―自給圏の終焉
終 章 大東亜共栄圏とは何だったか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
115
本書は、大東亜共栄圏を、「経済的自給を目指した圏域構想」と認識した上で、その経済圏構想が、戦争の遂行とともに政治的・軍事的に翻弄されてゆく歴史を冷静に描いている。開戦後に具体的な検討を始めるような泥縄的な構想であり、その後打ち出された圏内各国の自主独立を掲げる大東亜新政策も、欺瞞と独善に満ちた詭弁であったことが明らかにされる。昨今、太平洋戦争はアジアの解放戦争だと正当化する論調があるが、歴史的事実を客観的に積み重ねるこうした誠実なアプローチこそが、正しい歴史認識を導くと信じたい。とてもいい本だと思う。2023/12/28
skunk_c
82
終章に著者の立場が見事にまとめられている。「大東亜共栄圏」構想は1940年のドイツの西方攻勢による東南アジア植民地の流動化によるもので、1937年の日中戦開始以降の「場当たり的」政策のひとつだというのだ。大東亜建設審議会にいたっては対英米開戦後の「泥縄の対応」というのだから手厳しい。以上のように日本の戦争経済にいかにアジアを組み込むかという視点のもとに作られた共栄圏であり、その政治性の付け焼き刃な性格と、そもそも日本がそうした構想を維持できるほどの実力もなかったことをデータとともに明らかにしている。2023/02/07
HANA
59
「大東亜共栄圏」が欧米からのアジア開放を詠いつつ、日本が変わってその座に就くためのおためごかしだったのは周知の事実であるが、本書は従来イデオロギー的な観点から捉えられていたその言葉を政治・経済の面から検証した一冊。東南アジアをブロック経済圏として資源を輸入に頼らないという点は理解できるが、本書を読むとやってる事は泥縄そのものだなあ。骨子となる計画が無いまま各省庁の利権争いになり、戦争の悪化に伴いそれが悪い方向に変更されるのはブラックユーモア見ているよう。こういう従来から違った方向から読める本は良いなあ。2024/04/02
樋口佳之
59
それはそもそも、帝国日本が経済自給圏を運営するだけの経済力を、持ち合わせていなかったから/重光外交の表裏、対日協力者の表裏等々、空疎なアジア解放論の実相が読み取れる内容に学ばせていただきました。オビの赤字の真実だけは残念かも。なんでこんな事するかなあ。2023/03/06
なかしー
50
気になっていた日本のアジア支配構想。 理念は西洋支配からアジア解放と日本がアジアの指導的な立ち位置になると謳っている(後付け)けど、実際は端から東南アジアの資源狙いで西洋がやっていた帝国主義を日本がやっている落ちでしたって感じか?ま〜日本には資源がないからね…「貧すれば鈍する 鈍すれば窮す」を教訓通り体現している。2025/07/27
-
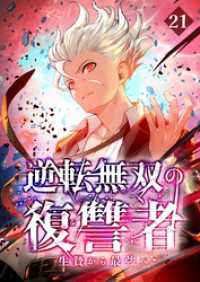
- 電子書籍
- 逆転無双の復讐者~生贄から最強へ~【タ…
-
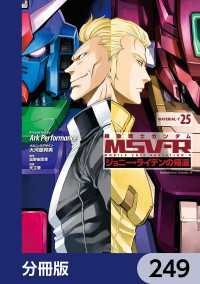
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー…
-
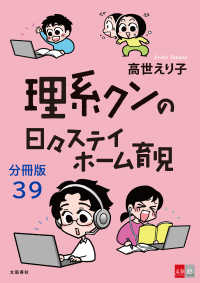
- 電子書籍
- 【分冊版】理系クンの日々ステイホーム育…
-
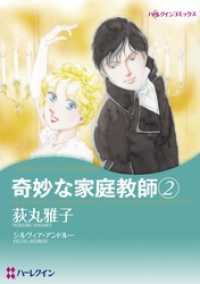
- 電子書籍
- 奇妙な家庭教師 2【分冊】 11巻 ハ…
-
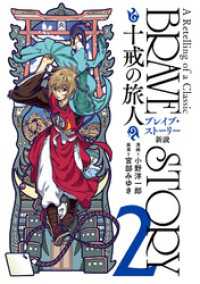
- 電子書籍
- ブレイブ・ストーリー新説 ~十戒の旅人…




