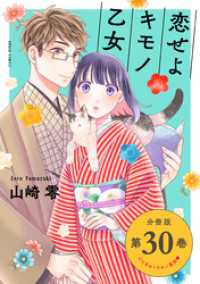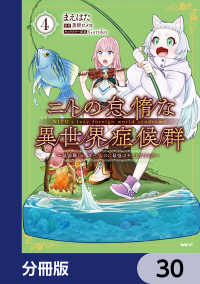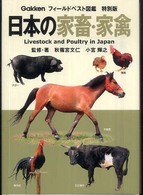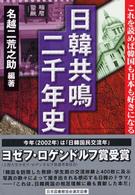内容説明
生きにくさの正体を動物行動学の視点から読み解き、生き延びるための道を示唆する。
家族は病気。頭がまわらず、たまっている仕事は進まず。
こんなことが同時にやってきたら………。
かなりへこむ。怖い。不安になる。
そんなときこそ、動物行動学・進化心理学の出番だ。
その不安や恐れは生存・繁殖にとって有利に作用するのか?
という視点から考えてみる。
この思考方法を知っているだけで、気持ちがラクになる!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
240
幸い「苦しいとき」ってのが余り無いのですが、Twitterでね「一生懸命書いた」とツイートされていたので、読んでみる事にしました。「自然の中で100人程度の集団をつくって狩猟採集を行う生活」に適応したヒトの脳は、ヒトが後天的に作り出した社会構造には、必ずしも適応的では無い場合もあるって事。また、脳にはクセがあるのでそれらを認識する事で、自身の置かれた状況下を客観視してみましょうねって事なのかしらね。図らずも、狩猟採集民の暮らしが書かれた本を併読していまして。かなりシンクロして、楽しい読書体験となりました。2022/11/26
アキ
110
6篇のエッセイからなる。動物行動学、進化心理学が専門の著者によると「ホモ・サピエンスの脳は、自然の中で100人程度の集団をつくって狩猟採集を行う生活という環境において生存・繁殖がうまくいくように進化してきた」らしい。その理論で言うと振り込め詐欺にひっかかる人は一万年前世界では生き延びる理由があると。情報が嘘である可能性を時間をかけて考えるよりも確証バイアス(ストーリーテリング・バイアス)を働かせ一瞬で判断を下す方が生存・繁殖に有利だったのではないか。うーん、どうだろう?ひとつの見方が得られる書ではある。2023/02/01
トムトム
16
みんなそう。良いときもあれば悪いときもある。自分以外の全てが幸せそうに見えてしまうこともある。人間だもの。キラキラしたSNSばかり見ているとそちらが普通かと思いこんでしまうかもしれないけれど、はたしてそうかな?落ち込んでもいいのさ!という本。2024/04/14
onasu
14
(繰り返し述べられる)人間は長い間「自然の中で100人程度の集団をつくって狩猟採集を行う生活」という環境に適応してきたので、現代の環境にそぐわない点があるのはおかしくない。 なんで、そこんところを人間も動物と、動物行動学的に解釈するというのはおもしろい。2023/02/20
to boy
10
著者の言いたいのは「自然の中で100人程度の集団を作って狩猟採集を行う生活」に適したホモサピエンスの生活様式(イコール遺伝子)がその後の人類の進化に追い付かず、現代もその遺伝子が我々の生活に根付いているということか。なかなか面白い考えで一理あると思った。不安、怒り、怯え、喜びなどの喜怒哀楽は当時の生活に必要な反応との事。何故に、類人猿時代での遺伝子で説明できるのかの説明がなされていない事には疑問が残った。それにしても文章がくどくて読むのに難儀しました。2023/09/02