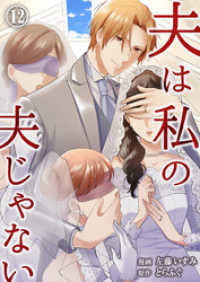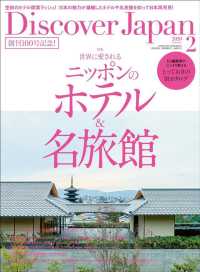内容説明
留学先のアメリカで孤独な日々をおくる19歳の尚美を救ったのは、多様な生徒が自ら運営する学生食堂〈サード・キッチン〉との出会いだった……仲間に支えられ成長していく姿に共感、感涙必至の青春小説!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜長月🌙
63
日本からアメリカに留学したナオミが体験する無意識な色めがね。それは自分に向けられるものでもあるし、自分が気付かずにいるバイアスでもあります。日本で生活していてもハーフっぽく見えることは誉め言葉としてよく使われます。そして多くの場合、手足が長いことや色の白さ、くっきり大きなふたえの目などを指します。「普通な」が「正常である」とか「正しい」という意味合いを持つことに懐疑的でなくてはなりません。2025/06/15
coolgang1957
52
青年は傷つきやすく臆病です、英語が拙くて言いたいことが伝わりません、バービー人形たちの間で劣等感に苛まされてます。でもそれは日本に居たって言葉が出ない、そんな状況は沢山ある、それに語彙が少なく的確な言葉を紡ぎ出せないのは同じ事、(このレビューも)。…でも舞台が留学中だからそんな光景が増幅されて心象がよくわかります。知る事が大事、無知は罪、と言われても勉強してないと理解はできませんよね。先生が言ってたように、考え続けないと…… 2023/12/04
seba
37
「エスノセントリズム(自民族中心主義)」という言葉を学んだという点で価値のある読書だった。時は1998年、ある人物の援助によりアメリカの大学への留学が叶った尚美。英会話の拙さにめげて馴染めないでいたところ、様々なマイノリティの学生が属する特別な学生食堂に呼ばれるようになる。しかし居場所を得た彼女が気付いたのは、自分が無意識に持つ差別意識だった。無知ゆえの差別を自覚した後にはすべきことがある。日本にいると切迫感に晒される機会が少ないため、無知でいることができてしまう。それは一つの特権だという言葉が印象的だ。2025/07/03
ゆみのすけ
29
読み応えがある、とてもいい本だった。アメリカの大学に留学したナオミ。英語に不慣れで、コミュニケーションがうまくとれないこと。他人の援助により留学生活を送るという経済面の厳しさ。それにより他人に揶揄され、差別されていると感じていた。息苦しい毎日に出会ったのがサードキッチン。そこは人種や性別などのマイノリティが集う特別な食堂。自分は他人を差別するわけがないと思っていても、無知ゆえに差別し、人を傷つけていることもあるなんて、考えてもみなかった。他人に目を向け、答えが出なくても考え続けることの大切さを知った。2023/12/24
鈴木拓
27
無意識のうちに人を差別していることは誰にでもあるのだろうし、それをすべて否定することもできない。むしろ、自分自身にもそれがあり、他の人にもそれがあるという前提で、どのように人と対していくのかを考える必要がある。それも自分自身の頭でしっかりと。自ら発する言葉に悪意がなくても、相手を傷つけていることがあるし、自分自身が傷ついていることもある。マイノリティ=アブノーマルではないし、違うことが当たり前なのだと頭では理解しても、きっと本質的に受け入れるのは簡単ではないのだろう。先入観を持たずに読んでほしい良書。2022/11/30


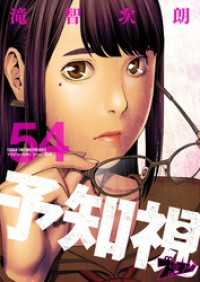
![中医臨床[電子版]通巻102号](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1079406.jpg)