内容説明
子どもに伝わる「教師の説明」を、徹底解説!
「教師の一方的な説明で進んでいく授業」からはもう卒業!
子どもをグッと引き付ける説明方法を大公開!
教師が具体例や実物を用いて、わかりやすく説明すれば、
子どもも「そうか!なるほど!」と納得感を持って、
教師の意図や伝えたいことが理解できます。
本書では、「子どもの理解を促す説明」「子どもの説明力を高めていく技術」を紹介します。
【目次】
第1章 説明とは?
1 教師の説明とは?
2 「授業での説明」の役割(1) 学習内容の理解を促す
3 「授業での説明」の役割(2) 学習内容を意義付ける
4 「授業での説明」の役割(3) 子どもの説明力向上
5 「授業での説明」の高め方
6 「学級経営での説明」とは?
第2章 子どもに理解を促す教師の説明 基礎編
1 理解を促す説明とは?
2 基礎の基礎――相手意識をもつことが第一―
3 基礎編(1)端的に・短くする
4 基礎編(2)結論を先にいう・全体像を先に示す
5 基礎編(3)具体例を出す
6 基礎編(4)理由・目的を伝える(趣意説明)
7 基礎編(5)あいまいな言葉を排し、具体的な言葉を使う
8 基礎編(6)子ども達に十分伝わる言葉を使う
9 基礎編(7)実物などを見せる
第3章 子どもに理解を促す教師の説明 応用編
1 理解を促す説明応用編の読み方
2 応用編(1)喩える
3 応用編(2)対比と類比
4 応用編(3)因果関係に気づかせる
5 応用編(4)対義語や類義語を用いる
6 応用編(5)極論・仮定を用いる
7 応用編(6)経験を想起させる
8 応用編(7)教師の経験を語る
9 応用編(8)学問の知見を生かす
10 応用編(9)体験をセットにする
11 応用編(10)挑発を入れる
第4章 子どもたちの説明力を高めていく指導技術
1 子ども達の説明力を高めていくことの意義とは
2 子ども達の説明力を高めていく指導技術(1)教師がモデルになる
3 子ども達の説明力を高めていく指導技術(2)子どもが説明する機会を授業で多くとる
4 「当たり前」「知っている」を説明させる
5 学級経営の場面でも説明させる
6 子ども達の説明への意欲を高める(1)説明の立候補を積極的に募る
7 子ども達の説明への意欲を高める(2)ハードルを上げ、評価する
8 良い説明の基準を明確にし、少しずつ指導する
9 どのような説明が出てきてほしいか想定して授業をつくる
10 クラスで良い説明について共有する
11 共有した説明の工夫を使う機会をつくる
12 書いて説明させる機会も多くとる
13 自分に自分で説明をさせる(1)
14 自分に自分で説明をさせる(2)
15 教師と子ども一緒に互いの説明力を高めていく
第5章 教師の説明力を高める小ネタ
1 説明力アップのための実践・微細指導技術
2 時間感覚を磨く
3 要約力を高める
4 間を恐れない
5 自分の説明を聞いてみる
6 「3」にこだわる
7 主語と述語は近くに置く
8 主語に「の」は使わない
9 曖昧な「が」は使わない
10 「~は!」を安易に使わない
11 使う言葉を動詞から動作表現に変える
目次
第1章 説明とは?
1 教師の説明とは?
2 「授業での説明」の役割(1) 学習内容の理解を促す
3 「授業での説明」の役割(2) 学習内容を意義付ける
4 「授業での説明」の役割(3) 子どもの説明力向上
5 「授業での説明」の高め方
6 「学級経営での説明」とは?
第2章 子どもに理解を促す教師の説明 基礎編
1 理解を促す説明とは?
2 基礎の基礎――相手意識をもつことが第一―
3 基礎編(1)端的に・短くする
4 基礎編(2)結論を先にいう・全体像を先に示す
5 基礎編(3)具体例を出す
6 基礎編(4)理由・目的を伝える(趣意説明)
7 基礎編(5)あいまいな言葉を排し、具体的な言葉を使う
8 基礎編(6)子ども達に十分伝わる言葉を使う
9 基礎編(7)実物などを見せる
第3章 子どもに理解を促す教師の説明 応用編
1 理解を促す説明応用編の読み方
2 応用編(1)喩える
3 応用編(2)対比と類比
4 応用編(3)因果関係に気づかせる
5 応用編(4)対義語や類義語を用いる
6 応用編(5)極論・仮定を用いる
7 応用編(6)経験を想起させる
8 応用編(7)教師の経験を語る
9 応用編(8)学問の知見を生かす
10 応用編(9)体験をセットにする
11 応用編(10)挑発を入れる
第4章 子どもたちの説明力を高めていく指導技術
0 子ども達の説明力を高めていくことの意義とは
1 子ども達の説明力を高めていく指導技術(1)教師がモデルになる
2 子ども達の説明力を高めていく指導技術(2)子どもが説明する機会を授業で多くとる
3 「当たり前」「知っている」を説明させる
4 学級経営の場面でも説明させる
5 子ども達の説明への意欲を高める(1)説明の立候補を積極的に募る
6 子ども達の説明への意欲を高める(2)ハードルを上げ、評価する
7 良い説明の基準を明確にし、少しずつ指導する
8 どのような説明が出てきてほしいか想定して授業をつくる
9 クラスで良い説明について共有する
10 共有した説明の工夫を使う機会をつくる
11 書いて説明させる機会も多くとる
12 自分に自分で説明をさせる(1)
13 自分に自分で説明をさせる(2)
14 教師と子ども一緒に互いの説明力を高めていく
第5章 教師の説明力を高める小ネタ
0 説明力アップのための実践・微細指導技術
1 時間感覚を磨く
2 要約力を高める
3 間を恐れない
4 自分の説明を聞いてみる
5 「3」にこだわる
6 主語と述語は近くに置く
7 主語に「の」は使わない
8 曖昧な「が」は使わない
9 「~は!」を安易に使わない
10 使う言葉を動詞から動作表現に変える
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちゅんさん
luckyair
surucucu
草食系教師
かるー
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】正ヒロインは愛する陛下に…
-
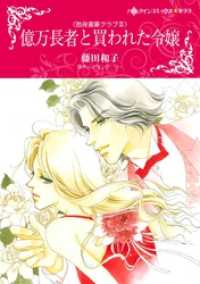
- 電子書籍
- 億万長者と買われた令嬢〈独身富豪クラブ…







