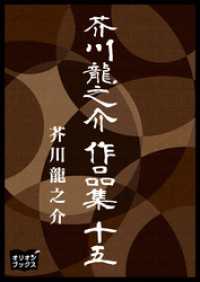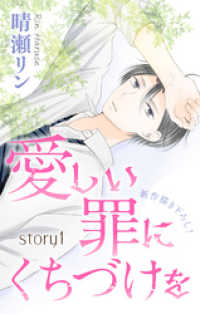内容説明
能力主義と自己責任、家族の多様化、ジェンダー不平等、承認欲求とアイデンティティ……。
現代の閉塞感に風穴をあけ「誰もが息のしやすい社会」を構想する希望の論考。
-
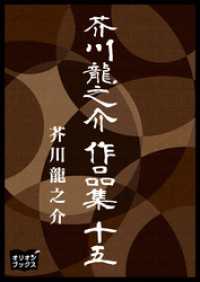
- 電子書籍
- 芥川龍之介 作品集 十五
-
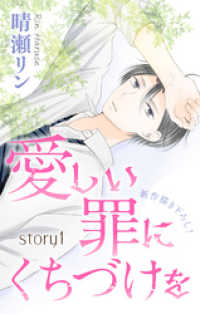
- 電子書籍
- Love Jossie 愛しい罪にくち…
能力主義と自己責任、家族の多様化、ジェンダー不平等、承認欲求とアイデンティティ……。
現代の閉塞感に風穴をあけ「誰もが息のしやすい社会」を構想する希望の論考。