内容説明
大正期から昭和初期のプロレタリア文学運動は労働者階級の現実を描く文学実践だが、そのジェンダー構造については十分に問われてきたとはいえない。プロレタリア文学をジェンダーというレンズを通してみたとき、階級と性にはどのような関係性が現れるのだろうか。
小林多喜二や徳永直、葉山嘉樹、佐多稲子、吉屋信子、山川菊栄など、大正から昭和初期の日本のプロレタリア文学を中心に、ジェンダー批評の観点からその実践を読み解く。弱者が権利を求める階級闘争の渦中でさえ、周縁化されたり、ケアとしての役割を求められたりする女性の姿を切り取る文学作品からは、階級闘争におけるジェンダー問題にとどまらず、「階級闘争自体のジェンダー化」というべき複合的な課題がみえてくる。
「階級」「労働運動」という論点とジェンダーやセクシュアリティ、さらに民族やコロニアリズムなどの論点の交差=インターセクショナリティにも着目して、プロレタリア文学が内包する問題と闘争の可能性を描き出す。
目次
はじめに 飯田祐子/中谷いずみ/笹尾佳代
第1部 プロレタリア文学場におけるジェンダーとセクシュアリティ
第1章 愛情の問題論――徳永直「『赤い恋』以上」 ヘザー・ボーウェン=ストライク[本部和泉訳]
1 コロンタイとコロンタイズム
2 『赤い恋』
3 徳永直の「『赤い恋』以上」
第2章 階層構造としてのハウスキーパー――階級闘争のなかの身分制 池田啓悟
1 ハウスキーパーをめぐる「ずれ」
2 辞書のなかのハウスキーパー
3 「仕事」と「身分」
4 ハウスキーパーを生きる
5 ハウスキーパーの始まりをめぐって
6 自主的人間の立場
第3章 プロレタリア文学における「金(ルビ:かね)」と「救援」のジェンダー・ポリティクス――「現代日本文学全集」第六十二篇『プロレタリア文学集』にみるナラティブ構成 飯田祐子
1 「救援」の対象――第一のパターン
2 プロレタリア文学における「金」
3 「金」とジェンダー・ポリティクス
4 「救援」の主体――第二のパターン
5 「救援」とジェンダー・ポリティクス
第2部 女性表象のインターセクショナリティ
第4章 女性表象の「輪郭」をたどること――山川菊栄「石炭がら」を起点として 泉谷 瞬
1 鉱山労働者と資本家の対立
2 危惧される「妻/母親」の存在
3 「女性」を表象することの困難
第5章 メディアとしての身体――葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」の女性表象 鳥木圭太
1 〈物流〉小説としての「セメント樽の中の手紙」
2 作品に描かれた階級意識
3 階級とジェンダー、あるいはジェンダー化される階級概念
第6章 吉屋信子の大衆小説におけるプロレタリア運動のジェンダーとセクシュアリティ――「読売新聞」連載小説『女の階級』 サラ・フレデリック[北丸雄二訳]
1 左翼運動と性差別
2 小説『女の階級』における「女の階級」とは何か
3 男の「同志愛」
4 「女の階級」という概念のなかの交差性(ルビ:インターセクショナリティ)
5 女の階級の結末――エス系の同志愛
第7章 朝鮮戦争期のジェンダーと帝国主義の記述――佐多稲子の場合 サミュエル・ペリー[大崎晴美訳]
1 ポストコロニアリズム、共産主義、占領期文学の時間性
2 佐多稲子、朝鮮、貫戦期
3 「白と紫」、帝国下のジェンダーとジャンルの攪乱
4 女言葉に潜む狂気
第3部 闘争主体とジェンダー
第8章 プロレタリアとしての娼妓表象――賀川豊彦「偶像の支配するところ」/松村喬子「地獄の反逆者」の行為性 笹尾佳代
1 賀川豊彦「偶像の支配するところ」の問題系
2 複層的な搾取の構造
3 娼妓労働作家による物語の流通
4 目覚める娼妓たち
第9章 残滓としての身体/他者――平林たい子「施療室にて」と「文芸戦線」 中谷いずみ
1 闘争主体としての「母」
2 純化されるイデオロギーと残滓としての身体
3 同室の女たちと「私」
第10章 闘争の記録を織りなす――佐多稲子「モスリン争議五部作」における女工たちの表象 李珠姫
1 全協と全労の対立――八重とタエ、そしてナカの人物造形を中心に
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田中峰和
冬峰
Э0!P!
takao
-
![愛の存在証明[1話売り] story11 ××LaLa](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1599803.jpg)
- 電子書籍
- 愛の存在証明[1話売り] story1…
-

- 電子書籍
- 発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸…
-

- 電子書籍
- 虎二先輩の飼育係 ベツフレプチ(4)
-
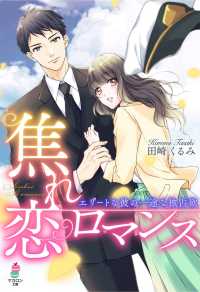
- 電子書籍
- 焦れ恋ロマンス~エリートな彼の一途な独…
-

- 電子書籍
- おかしな★ふたり プチデザ(18)




