内容説明
私たちはいつまで「できること」を証明し続けなければならないのか?
絶え間ない能力の発揮と成果を求められる現代社会。
「主体性」を祭り上げ、人々が互いにせめぎ合い、自己さえ搾取せざるを得ない社会構造。この現代の病理を特異な感性から解き明かし、「創造性」「和解」をもたらす新たな「疲労」のかたち――「なにもしない」ことの可能性を探る。
倦み疲れ、燃え尽きる現代社会への哲学的治療の試み
ドイツ観念論から出発し、現代思想界の先端を走るビョンチョル・ハン、その代表作にしてヨーロッパ20カ国以上で刊行されたベストセラー、待望の邦訳
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sayan
39
ドイツ哲学の旗手と注目される著者。我々は「能力」社会で、社会を変える力ではなく自らを搾取し疲弊させる能力に翻弄されると身も蓋もない。新自由主義に紐づけ、禁止の否定=規制緩和は多様な働き方をもたらすも、実際はWワーク無しでは困窮、成果をださないと次の契約がない、と不安に苛まれる状態を生んだ。この事は肯定的な力(計画、自発性、動機付け)に縛られ、死(鬱病含)に至るまで自身の最適化に明け暮れる、と著者の分析は容赦ない。「自己責任」という概念が下支えする能力社会と試読すると、私見だが著者の議論にリアリティが増す。2021/11/13
ちくわ
19
規制によって強制する社会から、自由な現代社会になったものの、自由になった現代は自分で自分を強制するようになってしまった。言っていることはシンプルでしたが、そこに気付くか気付かないかが、自分の身体や人生を守るための重要なポイントだと感じました。際限のない目標や計画といったプロジェクトに覆い尽くされた生活の中から、いかに、生き生きとした「今」を確保できるか。そのためには、やはりいったん立ち止まることが重要でしょうか。(☆5)2025/01/13
しゅん
15
原著は2010年刊行。現代は否定性ではなく、肯定性の過剰の社会となっている。その社会はマルチタスクの注意を個人に要求し、人は永遠に頑張り続ける。結果、人々はうつ病・注意欠陥多動性障害にかかる。否定性の病としてのウィルスではなく、肯定性の病としての鬱。アーレントの「活動的な生」とは交わらない疲労としての社会において、心の休息である「深い退屈」をいかに形成するか。著者の着点は、「疲労」をマイナスの機能だけでなく、人々をつなげるものであるというプラスの機能があるというところにいきつく。2023/02/28
コジターレ
10
僕たちは、立ち止まること、余白や無駄を味わうこと、何もしないこと、ぼーっとすること、一人で思索する時間を持つことなどを軽んじるようになってしまった。いや、できなくなったと言っても過言ではない。また、自由を得たはずなのに、その自由の奴隷になってしまっているとも言える。「無為」という自由な時間に不安を覚えるようになってしまったのだ。本書はそんな社会をいくつかの切り口で分析している。日々の生活の中で「何もしないことの価値」を見つめ直し、意識的にその時間を持ちたい。それが本来的には人間の進化の形なのだから。2024/10/30
mikio
10
新自由主義が体現する「能力社会」において、人々は自らの能力を絶えず発揮し、成果を求めて活動し続けなければならない。他者からの強制ではなく自由によって、自分自身と競争を続け、自分自身から搾取を続けることにより疲弊し精神疾患を患う。「能力社会」とは「疲労社会」にほかならないと著者は語る。この問題は格差社会にもつながるところがあると思うが、能力社会そして自由な社会とは、個への責任が増すということだから、イコール幸福感となるかは難しいところだ。難しい。2024/09/22
-

- 電子書籍
- 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者…
-

- 電子書籍
- あなたの世界で【タテヨミ】第38話 p…
-

- 和書
- 建築製図 (四訂)
-
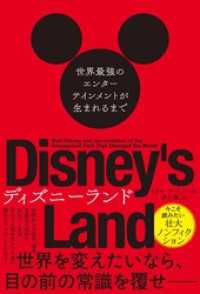
- 電子書籍
- ディズニーランド 世界最強のエンターテ…
-
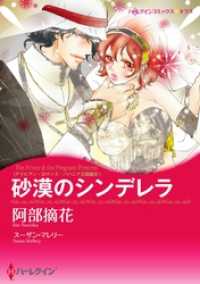
- 電子書籍
- 砂漠のシンデレラ〈アラビアン・ロマンス…




