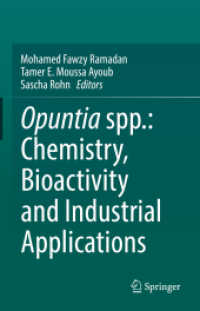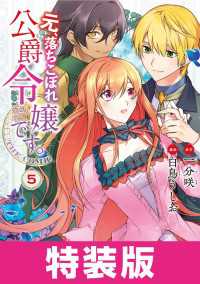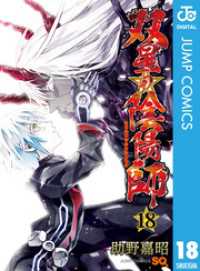内容説明
ASD/ADHDの大学教員、コロナ禍を生き、ウクライナ侵攻下のウィーン、アウシュビッツを行く。日常と非日常が交差する、はてなきインナートリップの記録。
10年ぶりにウィーンへ研究旅行に行くべく、羽田空港に赴いた著者を待っていたのは、出国許可がおりないというまさかの措置だった……。発達障害特性を持つ著者が、コロナ禍、ウクライナ侵攻の最中に、数々の苦難を乗り越え日本を出国し、ウィーンの研究者たちと交流し、ダヴォス、ベルリン、そしてアウシュヴィッツを訪問するまでの、めくるめく迷宮めぐりの記録。発達障害者には、日常もまた、非日常的な迷宮である。装丁・川名潤、装画・榎本マリコ。
「障害があるということは、ふだんから被災しながら生きているようなものだ。著名人の誰かがそのような発言をしたと思うのだが、(…)僕はこの言葉に大いに首肯できる。僕たちの日常は、災難だらけなのだから。障害者とは日常的な被災者なのだ。もとから被災していて、それだけでも大変なのに、疫病が流行し、コロナ禍の時代が出現した。(…)精神疾患の当事者がコロナ禍を生き、戦争を身近で感じた日々のちょっとだけ稀有な記録。それが本書の内容だ。」(「はじめに」より)
【目次】
はじめに──大学教員と精神疾患
第一章 コロナ禍時代の日常──京都にて
自助グループを主宰する発達障害者
基本、失敗の人生を生きている
好評を博した『みんな水の中』
「当事者研究」から「当事者批評」へ
研究の快楽
授業について
食べもののこと
「推し」に支えられて生きる
第二章 出国できませんでした──羽田空港での洗礼
いま海外って行けるんだ!
夢見心地の朝
大使館の窓口と格闘する
書類は揃ったぞ!
楽勝コースのはずだった
出国失敗
栗isうまい
第三章 中途半端な時期──ふたたび京都にて
立ちあがれ、オレよ
頭木弘樹讃
続・頭木弘樹讃
まさかの鼻血大出血、出発日前日の不眠
第四章 ウィーンとの合一──かつて帝都だった街で
ウィーンを体になじませる
中心街
住居とマスク着用義務
食と障害者モード
グリーンパス狂想曲
第五章 学ぶことを通じてのみ──教養体験、研究、外国語
美術とガラクタ
伝統音楽との戯れ
研究生活
「なろう系」としてのオーストリア語学習?
第六章 旅行と戦争──戦時下のアウシュヴィッツ訪問
各地への旅行(一) グラーツ、リンツ、ザルツブルク、インスブルック、クラーゲンフルト、ハルシュタット、メルク
各地への旅行(二) ダヴォスとベルリン
各地への旅行(三) ブラウナウ・アム・イン
各地への旅行(四) アウシュヴィッツ/ビルケナウ
帰国
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
くさてる
きゅー
shi 2
カエル子