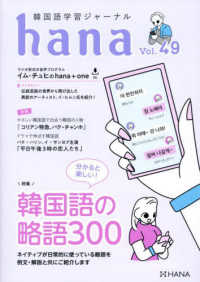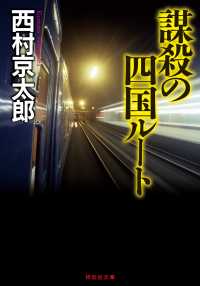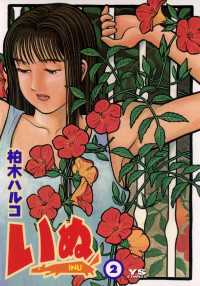内容説明
薩長の維新勢力から吹く風は、戦争だった。10年おきに戦争を起こし、ついに国を亡ぼした…。徳川発祥の地“朝敵”三河からはあたたかい平和の風が吹く。
(※本書は2015/9/1に株式会社 展望社より発売された書籍を電子化したものです)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
13
著者が三河の吉良吉田町あたりで生まれ、安城西尾らへんで育った。忠臣蔵の芝居小屋の放火の話や岩瀬文庫、明治用水は民間が作り上げたという記述は興味深い。三河とは維新によって虐げられ、出世が望めず国の支援も望めないため自力でもくもくと必要なことを成すが、それを宣伝することもない。自力で成すということは、他力を信じていないことでもあり、金はタンス貯金で銀行には預けない(笑)。三河に学校がないことを嘆く著者だが、愛知県で最も偏差値の高い高校は今や三河の岡崎高校であり、著者の通った高校も五本の指に入るのだ。2017/07/06
しみさん
6
自分と同じ出身地(愛知県西尾市)と知り、興味深く読みました。 徳川家の地元として明治政府に虐げられていたこと初めて認識しました。2017/07/30
plum
1
「思考の整理学」がよそ行きの顔をして棚に収まっている。1923愛知三河の生まれ。維新をゆるやかな革命と言う立ち位置である。近代の知識には生活がない→過去,現在,未来を考える役に立たない。対してことわざは,生活の中から生まれた知恵で,不偏性があるp158。外国文学に対峙する矜持。自分のいるところで自分の力でできるだけの仕事をするp182。アーサー・ウェイリーと「源氏物語」日本人は昔から競争が下手である。戦わずして勝つ。三河の風はそのような生き方を教えてくれるのである。2023/03/02
ゆきむすめ
1
タイトルに三河の文字を見つけて手に取ったが読みやすいのか読みにくいのかよくわからないうちに読了。自分が鈍感なのかな?あまり心に響かないエッセイだった。2016/07/27
しゅんぺい(笑)
1
なんでか、とことん読みにくかった。著者が愛知の三河出身だ、ということしか残ってない。2015/12/21