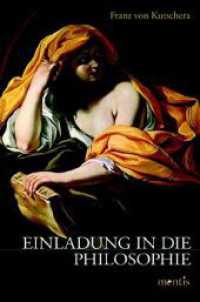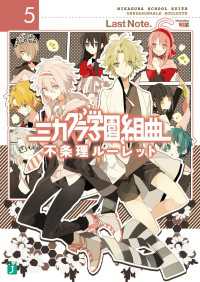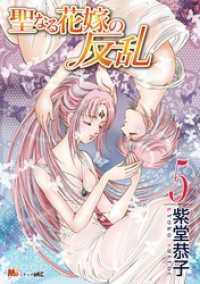内容説明
日本アニメーション学会賞2017受賞!
さまざまな潮流との接続のなかで新たな「アニメーション」の輪郭を引き直し、その現在と全貌、未来の道行きをも明らかにする独創的なアニメーション史再編の書、堂々の刊行!
本書は、世界の短篇・インディペンデントアニメーションの動向に精通し、理論と実践両面においてその最前線に立つ気鋭の論客による、渾身の現代アニメーション論である。
巨匠ユーリー・ノルシュテインの代表的作品『話の話』を糸口に、個人(インディペンデント/非商業的)作家たちの創造性の系譜と達成を読み解きつつ商業と芸術の壁を取っ払い、初期アニメーションからディズニー、アニメーション・ドキュメンタリーや世界の長編アニメーション、さらには宮崎駿・高畑勲など現代日本のアニメにまで、デジタル時代の新たな原理、古今東西のアニメーション表現を射程に、その可能性を理論的に追った雄渾の一冊である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サイバーパンツ
14
現在のアニメーションは主に、商業/アート/(ウェブ)に分けられるが、実質これらに明確な境界線はない。本書はノルシュテインによる謎めいた短編アニメ『話の話』を中心としながら、その謎の理由を「個人的」であること、原形質的であることに見出し、またそれを軸として、前述したように曖昧なままにジャンル分けされてしまったことで、アニメーションの中で見えなくなっていたものを見つけ出す、アニメーション史再編の書である。2017/03/25
しゅん
10
「個人的」であるからこそ開かれている、という逆説を丁寧に論じて惹かれた。アニメーション論であると同時に映画論でもある(その二つが不可分なのではないかという視点も提示している)。記号操作によってイメージを鑑賞者の中で呼び覚ます、という意味でノルシュテインがアニメーションを映画より小説に近いと主張しているのは面白かったな。2018/08/03
gu
5
アニメ批評の勉強に読んでみたが、思っていたより人文学方面に繋がる議論が展開されていた。アニメーション映画とは実写映画よりも文学や演劇に近い芸術であるということ。個人的でありながら多種多様な読者を包みうる一人称小説の「わたし」の機能を連想した。今ここではない時間や人、つまり幽霊をメタファーによって呼び起こしうる「個人的」なアニメーション表現について、その土地に根付くとはその土地の幽霊が見えるようになるということだという、管啓次郎の著作の文章を思い出した。2024/01/01
ウインド
2
ちょー大雑把に言えばノルシュテインの『話の話』を取っ掛かりにすることで、【1】コマ撮り(フレームの間)に「個人的な」ものを、【2】原形質性やデジタル技術(フレームの上)に「ハーモニー」を見いだし、【3】そしてそれらがメタファーとして別の世界(フレームの向こう側)と関係性を結ぶことを論じている。本書で挙げられてる以外のかなり複数の作品に対しても理解が深まるはずの良書。著者直々の要約レジェメもあるのでそちらも併せれば読む助けになるはず。2017/07/15