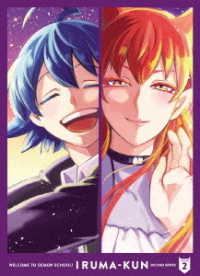内容説明
生前にはアメリカの医学界を陰で支配しているとまで言われながら、没後はその名さえ忌み嫌われたハリー・スタック・サリヴァン(1892―1949)。1970年代にアメリカ精神医学の源流として再評価され、さらに近年、人間社会と精神疾患の関係を論じた先駆者として再注目される精神医学者の、本邦未訳の論考を中心とした著作集。
サリヴァンが生涯をかけて訴えたのは、人間同士の差異よりも、互いを結び付けているものに着目することの重要性だった。患者一人ひとりを診るのではなく、「人間集団に対する精神医学」を唱えたのである。しかし、「個性とは幻想である」という見解は当時、あまりにラディカルでほとんど危険思想のように受け取られた。今世紀になり、「トラウマ理論」や「発達病理学」といった学際的研究領域が確立してようやく、サリヴァンの提出した課題に科学として取り組めるようになったのである。
本書は、初出出典に基づいて訳出した日本語版オリジナルの論集で、徴兵選抜、戦時プロパガンダ、反ユダヤ主義、国際政治など、実社会に関する特に重要なものを選んだ。収録した12編のうち11編は、日本で唯一未訳の著書“The Fusion of Psychiatry and SocialSciences” にも収められている。
なお、編訳者の阿部大樹氏は、サリヴァン『精神病理学私記』で日本翻訳大賞を受賞。今年10月に京都で開催される「サリヴァン・フォーラム」にも登壇する予定。
目次
編訳者まえがき
第一部 精神医学とは何か
精神医学入門三講
社会科学百科事典『精神医学』
黒人青年についての予備調査
症例ウォレン・ウォール
個性という幻想
不安の意味
第二部 精神医学の応用
プロパガンダと検閲
反ユダヤ主義
精神医療と国防
戦意の取扱いについて
リーダーシップの機動化
緊張――対人関係と国際関係
索引
目次
編訳者まえがき
第一部 精神医学の基礎篇
精神医学入門三講
精神医学ーー『社会科学百科事典』より
黒人青年についての予備調査
症例ウォレン・ウォール
「個性」という幻想
不安の意味
第二部 精神医学の応用篇
プロパガンダと検閲
反ユダヤ主義
精神医療と国防
戦意の取扱いについて
リーダーシップの機動化
緊張――対人関係と国際関係
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Z
フクロウ
エジー@中小企業診断士
Starr Stream
small_akuto
-

- 電子書籍
- 大好きな婚約者様、もうお別れしましょう…
-

- 電子書籍
- ペンにりぼんを~漫画家・井出智香恵物語…
-
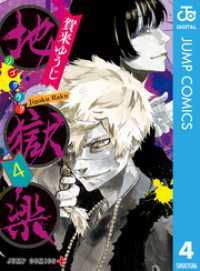
- 電子書籍
- 地獄楽 カラー版【タテヨミ】 90 ジ…
-

- 電子書籍
- ヒロイン?聖女?いいえ、オールワークス…