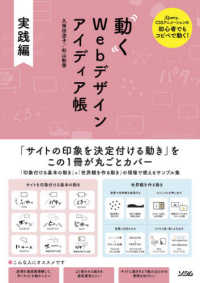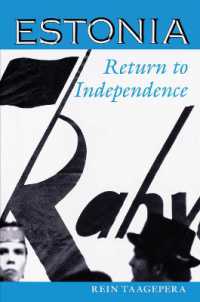内容説明
翻訳者としての福沢諭吉は、何を、どのように訳し、何を訳さなかったのか。
幕末~明治初年、福沢諭吉が読み込んだ西洋の書籍と、それを翻訳・翻案して刊行した書籍の文章とを丹念に検討し、そこにあらわれる翻訳思想、西洋の近代的概念の受容・変容過程を読み解く。
目次
序
凡例
第1章 人種観――S. A. ミッチェル問題
一 はじめに
二 福沢とミッチェル
三 福沢の継承と削除
四 おわりに
第2章 人間観――権利、義務、労働
一 はじめに
二 『西洋事情』外編
三 『西洋事情』二編「巻之一」
四 労働問題:学問と労働
五 おわりに
第3章 中産層育成構想
一 はじめに
二 福沢の中産層育成構想
三 中産層への着目過程
四 福沢の中産層構想の特徴
五 おわりに
第4章 民権認識と初期思想――『学者安心論』を中心に
一 はじめに
二 福沢の自由民権運動評価
三 初期思想との関係
四 おわりに
第5章 自然権主義と経験主義の受容――「公理」と「功利」問題
一 はじめに
二 自然権主義の「公理」と経験主義の「功利」
三 福沢の自然権主義受容
四 自然権思想の功利的受容の背景
五 おわりに
第6章 西洋思想受容の方法論――「分限」
一 はじめに
二 方法論としての「分限」
三 思想としての「分限」
四 おわりに
あとがき
参考文献一覧
索引
-

- 洋書
- Études I…
-
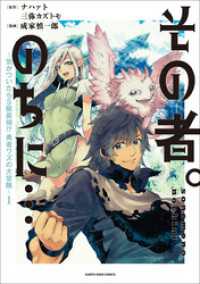
- 電子書籍
- その者。のちに… ~気がついたらS級最…