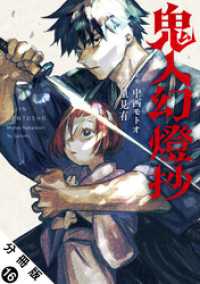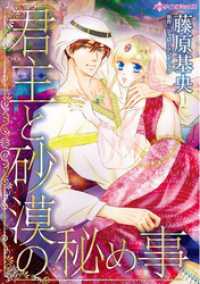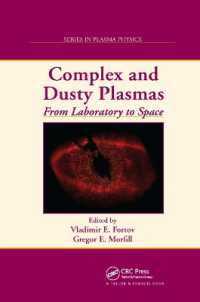内容説明
大阪や東京日本橋界隈の問屋、観光地の朝市、縁日、門前町の商家など、その源流をさかのぼると、多くは中世社会にまでたどり着く。そして彼らの営業形態や商売人としての思想には、中世から引き継がれたものも少なくない。いわば現代経済社会の基礎は中世の商業社会にあるといえよう。本書は長く商業史を牽引してきた著者が、中世の個々の商人像にスポットライトをあてつつ、経済全体の流れについても描いてみせた商業史入門の傑作。朝廷に仕えた供御人、大原女などの行商人、都市の定住商人、戦国の豪商等々、さまざまな商人のしたたかな営業活動が、活き活きと浮かび上がる。
目次
はじめに
概観
研究史の流れ
中世商人の諸身分
行商の諸類型
中世都市の商人
座の商人
戦国の豪商
海の商人たち
1 中世商人の諸身分
官衙所属の諸商人
中世商人の身分的外被
粟津橋本供御人
遍歴する灯炉供御人
禁裏駕輿丁の諸商人
社寺奉仕身分の商人たち
神威ふりかざす商人・神人
御師と山伏
遍歴の高野聖
荘園制的諸身分の商人
名主的・農民的商人
播磨国矢野荘の名主的商人
荘官的商人
山科七郷商人
2 行商・遍歴の商人たち
伝説のなかの旅商人
行商の二つの姿態
商人首領八郎真人と水銀隊商
金売吉次伝説とその背景
地域社会の行商人
都市近郊行商人─大原女と桂女
定期市の行商人
職人歌合の行商人
中世日本のキャラバン
都鄙を往来する行商人
荘園を遍歴する商人たち
戦国時代の遠隔地行商人
『多聞院日記』の行商人たち
旅商人たちの掟
自衛と相互扶助
山賊・海賊・関所とライバル商人
山越四本商人の掟書
3 都市の商人
都市の商人と町人
商人と町人
見世棚から店舗の商人へ
都市の座商人
土倉と酒屋
京都の土倉
六星紋の柳酒
土一揆の嵐の中で
京の長者たち
長者の出現とその歴史的背景
茶屋と後藤
角倉の多角経営
4 座商人
座の起源と特権
座とギルド
座の起源と性格をめぐる論争
商人座の特権
都市の座
祇園社の綿本座と新座
京の米場座と塩座
奈良の符坂油座
村落の座
大和国乙木荘の簾座
摂津国深江村の菅笠座
近江国保内座商人
大山崎油神人
大山崎油神人の負担と特権
営業圏の拡大と地方油商人との対立
大山崎油神人の構成
5 戦国の豪商たち
東国の豪商
会津の簗田氏
小田原の薬種商外郎氏
佐竹領国の御用商人
甲駿越の豪商
越後府中の蔵田氏と甲斐古府八日市の坂田氏
駿府今宿の友野・松木氏
信長と御用商人
尾濃両国商人司伊藤氏
越前北庄の橘屋
堺の今井宗久
6 海の商人
中世の水運と商業
浦舟と津軽船
越前敦賀の舟道座
廻船式目の成立
堺の豪商たち
自治と文化
備中屋と湯川宣阿
天王寺屋とその一族
小西隆佐と行長
博多の豪商
僧形の商人宗金
神屋寿貞・宗湛
島井宗室
参考文献
関連年表
解説 商業の時代としての中世(中島圭一)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera