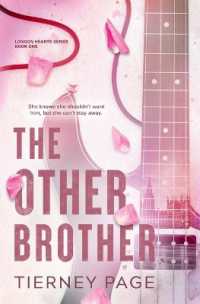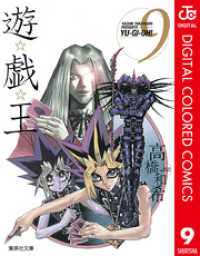内容説明
清朝中国から台湾を割譲させた日本は、植民地・台湾を統治するため新たな統括官庁を組織した。その現地機関が台湾総督府である。初期武官総督時代・大正デモクラシー期の文官総督時代・大戦期の後期武官時代を経て、植民地時代の終焉までの日本支配の全貌を追うとともに、その軍事権・行政権・立法権・司法権の実態を探る。そこで浮き彫りにされるのは、台湾人としての民族意識が自治権獲得に向けた運動と併行して日本統治期に醸成された、という史実だ。台湾独立運動家でもあった著者が、多面的な視点をもって、平明かつ詳細に書ききった名著。
目次
地図
はじめに
序章 日本と台湾
台湾獲得 日本の領土拡大とその破綻 台湾人意識の形成 日本離脱後の台湾 支配者変われど…
1 台湾領有
緊迫下の授受手続き
樺山全権の任命 割譲反対にわく台湾へ おびえる清国側全権 異例の洋上会談 第二回会談
台湾攻防戦
独立への胎動 台湾民主国成る 台北城の陥落 各地の抵抗運動 台湾民軍の敗北 台湾民主国と台湾総督府
領有の確立
境界の設定と不割譲宣言 不平等条約の処理 国籍選択 意外に少なかった退去者
2 初期武官総督時代
暗中模索
初期武官総督の顔ぶれ 樺山総督 桂・乃木総督 無能な水野・曾根民政局長 抵抗運動の鎮圧 高野孟矩事件
児玉総督と後藤新平
児玉・後藤コンビ 阿片漸禁政策 支配の基礎づくり 交通網の建設 製糖業の振興 財政独立の実態 抗日ゲリラ対策
弾圧と建設
佐久間総督 めまぐるしい民政長官の交替 高砂族などの鎮圧 安東総督と明石総督 西来庵事件 下村長官の誕生 建設と収奪
3 文官総督時代
大正デモクラシー期の総督群像
文官総督への移行 台湾軍司令官制度 政友会系の田・内田総督 有能な長官と汚職長官 憲政会の伊沢総督 総督府人事の紛糾 上山総督 台湾銀行事件 川村総督と河原田長官 民政党の石塚─人見体制 霧社事件
台湾人の政治運動
林献堂と台湾同化会 啓発会から新民会へ 台湾議会設置運動 総督府による評議会と協議会の設置 台湾文化協会の結成 台湾共産党 政治運動の弾圧
満州事変後の総督たち
太田・南総督 異色コンビ──中川総督と平塚長官
文官総督支配の実際
同化政策 内台人融和策 地方制度の改正 実体なき地方自治 台湾人官僚の登用
4 後期武官総督時代
戦争下の台湾総督府
予備役提督の小林総督 日華事変の波紋 日本帝国の手先と軍夫 皇民化運動 「改姓名」の布告 長谷川総督 安藤総督 皇民奉公会 南進基地化
大戦下の台湾人
経済事情の逼迫 「志願兵」から徴兵へ 〝日本軍人〟として まぼろしの国政参加 あいつぐ叛乱容疑事件 運命のカイロ声明
躍進の実態
教育・公共事業の充実 農業の発展 工業生産力の増大 徹底した財閥庇護
5 台湾総督府の権力
台湾総督の地位
中央主務官庁 朝鮮総督との比較
軍事権
軍政・軍令両権の掌握 文官総督以降の軍事権消滅
行政権
民政(総務)長官の職務権限 総督の人事賞罰権 命令発布権
立法権
初期の植民地法制 六三法──律令制定権と緊急命令権 三一法──法律の優位 法三号──補完的律令 立法権行使の実際
司法権
苛酷な対台湾人刑罰規定 裁判官・検察官任命権
「台湾の土皇帝」
総督は土皇帝 巨大な官庁組織 警察は権力の権化
6 台湾総督府の終焉
最後まで残った差別
台湾在住日本人の推移 日本人渡台の動機 台湾語の習得 「内地人」と「本島人」 台湾人蔑視と差別待遇 「本島人」を締め出した官庁 教育差別
五〇年にわたる支配に終止符
日本の敗戦 国府の台湾占領 統治権力の引き継ぎ 台湾人も敗れた 「日本色」の一掃 日本人の引揚げ
主要参考文献
解説 檜山幸夫
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
さとうしん
nagoyan
スプリント
nnpusnsn1945