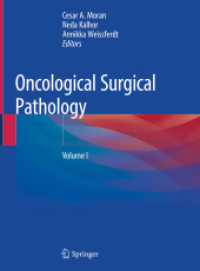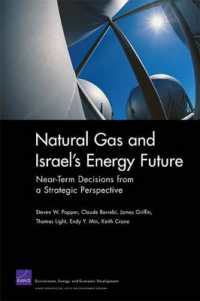内容説明
日本の気候は、5000万年前の超温暖期から3000万年前の寒冷化、2300万年前のモンスーン開始による梅雨の誕生、エルニーニョ多発の時代、260万年前の氷期など、さまざまな変化を経験してきた。そうしたなかで、日本は列島を形成し、日本特有の温暖湿潤で美しい四季をもつ気候となってきた。5000万年前には大陸の一部だった日本が、大陸から分かれ始めたのは約4000万年前、日本列島が現在の位置になったのは約1500万年前だが、その長い時代の変遷の中で、日本の気候はどのように変化してきたのだろうか? 気候は、日本だけでは語ることはできない。日本の気候の成立には、ヒマラヤ山脈の誕生によるモンスーンの開始や黒潮と対馬海流の成立も大きく関わっている。本書では、地球全体の気候変動、日本列島の地質学的な変化と気候の変化を関連づけて明らかにしていく。
主な内容
第1章 超温暖期とその後の寒冷化 日本列島以前の気候
第2章 モンスーン時代の到来 梅雨の始まり
第3章 日本列島誕生と気候への影響
第4章 地球温暖化アナロジーの時代
第5章 第四紀氷河時代の日本
第6章 日本特有の気候の成立
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
115
梅雨や多雪など四季折々の変化に富み、地域ごとに異なる森林帯が広がる自然を生んだ日本特有の気候は、数千万年に及ぶ地球規模の地殻と気象変動の果てに奇蹟的に成立したものだった。氷河期と温暖期が繰り返され、列島成立に伴う海流の変化やヒマラヤ山脈誕生によるモンスーン発生などの条件が積み重なり、世界でも稀な水と緑に恵まれた4つの島を生んだのだ。この島々に抱かれて独自の気風を育んだ日本人は、いかにして自分たちの文化が生まれたのかを考えねばならない。現在が永遠には続かないことは、日本の大地そのものが証明しているのだから。2022/11/03
やいっち
72
十日ほど前に読了の保坂 直紀著『地球規模の気象学 大気の大循環から理解する新…』(ブルーバックス)に引き続いて気象気候もの。保坂氏本は気象を太陽系も含めた空間的に把握。佐野氏らの共著は、5000万年の長い歴史という時系列で解き明かしている。2024/02/25
アナクマ
36
落ち着いた筆致で日本列島の気候の移り変わりを解く。科学的慎重さと情報量を保ちながら親しみやすい読感。◉最終7章_は過去1万年。最終氷期が終わり農耕が始まっても、一時的な寒冷化で縄文の三内丸山は滅び、弥生の濃尾平野では稲作が放棄された。天明の飢饉1787-はアイスランドの噴火が原因だ(火山噴火は短期的/数年は寒冷化を、長期的/数万年間には温暖化を起こす)。生物が翻弄される。◉科学は積み重ね。実際に起きた現象をひとつひとつ検証・確定し、世界の成り立ちを知る行為。そして私たちの行く末を見晴るかす。読経にも似る。2024/04/30
nagata
14
南極見学ついでに手にした本。初回は流し読みで終わってしまったが、日本が大陸から列島になるころから気候がどのように塗り重ねられて現在の姿になったのかをたどることができる。火山活動であったり、植物の繁栄であったり、これまでは1000万~数百万年単位での遷移だったのが、ここ最近は目まぐるしく変動しているようにみえるのは、観測精度がそこそこ上がったからなのか、そもそも間氷期からの変動期に入ったのか。いずれにせよ、自然の動きに無関係ではいられない。2024/06/23
やいっち
14
昨夕読了した。五日ほどを費やして。十日ほど前に読了の保坂 直紀著『地球規模の気象学 大気の大循環から理解する新…』(ブルーバックス)に引き続いて気象気候もの。保坂氏本は気象を太陽系も含めた空間的に把握。佐野氏らの共著は、5000万年の長い歴史という時系列で解き明かしている。2024/02/25
-
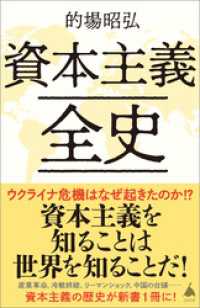
- 電子書籍
- 資本主義全史 SB新書