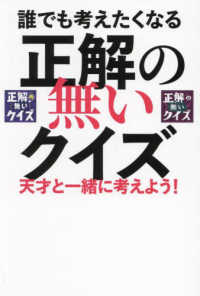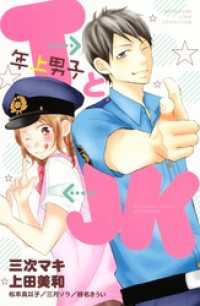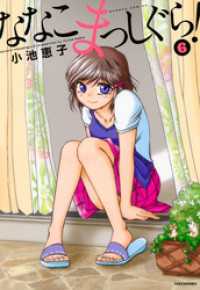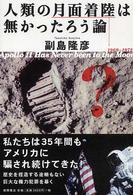- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本では古来さまざまな形で書籍が蓄積され、八世紀の芸亭以来、書籍の公共圏として図書館がつくられてきた。明治に導入された西洋式の図書館は、占領期にGHQの改革で日本の民主化のために万人に開かれた公共図書館のシステムへと再構築されようとしていた。その推進者キーニーの改革は挫折したが、誰もが知る権利を行使できる知の公共圏としての図書館が今こそ求められる。古代から現代まで日本文化を形成してきた図書館の歴史を繙き、これからの図書館のあり方を考える。
目次
はじめに
江戸時代までの「書籍の公共圏」
明治から戦後にかけての図書館政策
高度経済成長期以降の図書館と今後の課題
文化を創造し次世代に伝える図書館へ
第一章 古代──書記文化の誕生から和本の成立まで
1 言葉と文字──日本語と日本文明圏の出現
日本文化圏への文字の伝来
文字はいつから使われるようになったのか
漢字の活用──試行錯誤の中で
漢字から仮名へ──国風文化の確立と日本文明圏の出現
2 日本最古の図書館「亭」
仏教書・儒書の伝来
文字・書籍による学習の広まり
日本最古の「文の庫」──亭と石上宅嗣
亭に影響を受けた賀陽豊年、菅原道真および空海
3 和本の成立
国風文化の興隆と大陸の情勢
かな文字と女房文学の発展
王朝文学・国風文化のスポンサーとしての藤原道長
和本の誕生
藤原定家の貢献
漢文とかな──日本文化の二重構造
4 平安朝のふみくら
国・官の文倉
教育機関の文倉
寺院の文庫・経蔵
個人文庫
蔵書の保存
時代の変化に伴う文庫の変化
第二章 中世──武家文化における書籍公共圏
1 武家文庫と教養への目覚め
武家文化における出版とその集積としての武家文庫
武士階級の教養の高まり
2 鎌倉新仏教の発展と武家文化
鎌倉新仏教の武士・庶民階級への浸透
禅宗の伝来と発展
朱子学の到来
武家文化の興隆
高まる学問・文学への関心
軍記物の隆盛と歴史書
3 五山文化
五山文学と出版文化
寺院文庫の発達と学芸の普及
五山の出版から嵯峨本へ
4 武家社会における書籍公共圏──金沢文庫・足利学校
本朝書籍目録
金沢文庫
足利学校
地方への出版文化の波及──堺における出版業の出現
第三章 近世──出版文化の発展と教育改革
1 古活字版から整版印刷へ
出版業の発展と文化の興隆
書物問屋と地本問屋──三都の本屋
戯作文学の誕生
貸本屋・古本屋
古活字版の時代
2 江戸時代の教育と文化
武士階級の教育体制──幕府学問所と藩校
元禄文化
寺子屋と郷学
代表的な郷学
官許学問所としての懐徳堂
幕府学問所と各藩藩校・西洋医学教育機関等での教育と研究
天保の改革期における教育改革
3 江戸時代の文化サロン
木村蒹葭堂
蔦屋重三郎
塙保己一
4 紅葉山文庫と書物奉行
将軍のアーカイブス
青木文蔵敦書
近藤重蔵守重
高橋作左衛門景保
5 大名文庫・公開文庫
主な大名文庫
主な公開文庫
国学の誕生
第四章 幕末・明治・大正──書籍公共圏・近代的図書館の成立
1 幕末から明治へ
幕末・明治初期というひとつの流れ
活字印刷の台頭による本屋仲間の衰退
明治期における出版の変化
2 明治期の教育体制の確立・整備
明治黎明期における学校制度の整備
外国語書籍の移入とその受容
官民における教育機関の拡充
3 日本の科学技術力はいかにして向上したか
幕末の洋学の教育体制
諸藩および民間における洋学の教育
大学制度の確立・発展と岩倉使節団の功績
草創期の社会教育──博物館と図書館(書籍館)
4 近代西欧型図書館の紹介
福澤諭吉と「ビブリオテーキ」
書籍館と町田久成
書籍館開館と町田・田中論争
帝国図書館と田中稲城
「図書館」という語の確立
日本の図書館学と和田万吉
青年図書館員連盟と間宮不二雄
5 書籍公共圏の書誌調整──『古事類苑』の編纂と発行
書誌コントロール
『世界書誌』と『百科全書』
日本における百科事典刊行の動き
書誌データ編纂の動き──『群書類従』から『国書解題』、『国書総目録』へ
第五章 昭和・平成──紙からデジタルへの知的公共圏の発展
1 帝国図書館から国会図書館へ──昭和戦前期~戦後の動向
松本館長の下での帝国図書館
文部省の読書運動と中田邦造
国立国会図書館の創設と帝国図書館の吸収
日本図書館協会
図書館職員養成所
2 国立国会図書館(NDL)ができるまで
国立国会図書館の設置と図書館法
国立国会図書館設立までの経緯
3 図書館に関係する占領政策
占領軍による日本弱体化計画
占領政策によってもたらされた言語空間
図書館員のキャリアの問題
図書館のあるべき姿とは
4 キーニー・プランとCIE図書館
米国型の公共図書館の導入とキーニー・プランならびに金曜会
CIE図書館がもたらしたもの
5 アメリカ型図書館の日本での浸透──福田なをみの影響と業績
福田なをみの生涯
占領軍図書館政策の日本側との橋渡し役として
国際文化会館図書室長としての働き
6 高度成長期の日本の図書館
CIE図書館と日本の専門図書館
ドクメンテーション(documentation)活動の普及
7 ジャパン・ライブラリー・スクール(JLS)
設立までの経緯
JLS設立とその後
JLS卒業生の活躍
8 図書館界を取り巻くさまざまな問題点
日本図書館協会の機能不全ならびに図問研と『中小レポート』
プロフェッショナルとしての司書と指定管理者制度
文部省の学術情報センター構想
NDLの日本全国書誌のその後の発展と「古典籍総合目録」
第六章 二一世紀の図書館を考える
1 記録文化の進化史
日本文化を発展させてきた記録文化
近現代の活字・印刷技術の革新
2 米国型図書館の功罪──占領期の図書館改革・再考
占領期から現代までの図書館の変化と課題
リベラル・デモクラシーの基盤としての公共図書館
パブリック・サービスの充実と重視
CIE情報センター(図書館)の影響──専門図書館のサービス改革への貢献
3 図書館のあるべき姿を求めて
無料貸本屋から「新しいライフスタイル実現の場」へ
PFIと指定管理者制度──自助・自律的な図書館のあり方
図書館空間の再検討と躍進──ライフスタイルの提案から自己確立の場へ
デジタル社会における図書館の意義
図書館は文化の礎、司書は知の伴走者
あとがき
主要参考文献
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
よっち
サケ太
つーちゃん
そうたそ