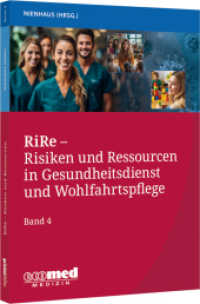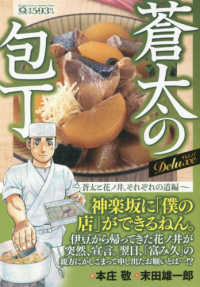内容説明
清盛ら平家一門が権力を握り、日本史の主役を務めたのはわずか十数年。だが平氏の存在感は大きい。「源平合戦」で功績を挙げて鎌倉幕府を支えた御家人(北条氏、梶原氏、三浦氏など)の多くは平氏出身とされ、後世の織田信長も平氏の末裔を称した。本書は、平朝臣の姓を賜った天皇の子孫たちに始まり、朝廷に対して反乱を起こした平将門、公卿・実務官人として京都で活躍した堂上平氏など、公家・武家にわたる平氏の全貌を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
113
源平合戦で完全に滅びたとされる平氏だが、実際に滅んだ清盛系以外にも平氏を名乗る公家や武家がいた。しかし夥しいほどの家系に分岐して全国に広がり、頼朝に味方し鎌倉幕府成立に貢献した御家人の多くが北条氏を筆頭に坂東平氏を自称し、実質的には平平合戦であったとは。藤原氏や源氏を含めて数氏の家系がこれほど歴史を大きく左右した例は他国にはなく、易姓革命や共和政体を経験していない日本ならではの現象か。そんな平氏の全貌を把握するのは頭が痛くなるが、彼らの盛衰や興亡が日本史を動かしたというより引っかき回した状況が見えてくる。2022/09/23
六点
96
さて、この本を読んで、中公新書から出ております、蘇我氏、藤原氏、源氏と全て読んだことになります。何れの本を読んでも似たようなお名前が大量に出て参ります。この本もそれに負けず、たっぷり系図と似たようなお名前が出て参ります。華やかに栄えそれ故に早く滅んだ武家平氏と言うか、伊勢平氏と、明治まで生き抜き、その伝統を後世まで伝えた公家平家の根強さには感嘆に値します。さて、再度角田文衛の『平家後抄』ても読みますか、積読山の何処かに埋もれているいう・・・。2024/04/26
ホークス
40
2022年刊。天皇の子孫である親王や王は、臣下になる際に賜姓された(橘、在原、源など)。平姓は平安期の四天皇(桓武、仁明、文徳、光孝)の一部子孫に与えられ、特に桓武平氏(清盛や将門)が有名。桓武平氏には武の系統と別に、明治維新まで続く官吏の系統もある。武士の台頭は、一部の源氏や平氏等が軍事を家職とする軍事貴族化した事に始まる。官職や藤原宗家の権威を後ろ盾として根拠地を支配し、養った兵力や財物で権威側に私的な奉仕をする相互関係を築いた。武士の世への契機は、白河上皇が自ら武士に命令し始めた辺りらしい。2025/06/05
Toska
24
仁明天皇の系図(53頁)などを見ると分かりやすいが、子・孫の世代が源氏を賜っているのに対し、平氏は曾孫の代から。つまり平氏は源氏よりも天皇から等親が離れるわけで、世代が進むにつれての没落もそれだけ早かった。本書ではそうした無名な平氏の末裔が列挙されるから、人によっては退屈と感じるかもしれない。ただ、そうした無名性こそが平氏の本質でもあるのだろうし、そこから這い上がってきた伊勢平氏の栄華が同時代人にインパクトを与えた理由がよく分かる。2024/12/02
鯖
24
平氏の栄枯盛衰を追って、様々な人々の生涯を羅列していく本。平氏が王権を牛耳ったのはホントに十数年だけども、時忠の叔父信範の家系の堂上平氏は現在まで血脈を保ち続けている。「父祖の日記を書写し、平記にしたためた信範の子孫にふさわしい」とのことで、ギーヴとファランギースが生き残ったのは正しかったんじゃな。吟遊詩人は生き残る。壇ノ浦後の関東における坂東平氏の粛清粛清粛清について「日頃平安貴族を研究している身としてはおおこわといった感があるが」ってあって笑っちゃった。先生、突然の後鳥羽ムーブやめてください。2022/10/31
-

- 電子書籍
- ダンジョンのUX、改善します! 連載版…
-
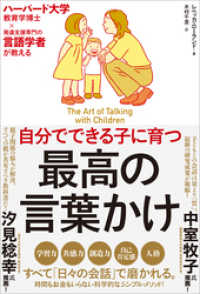
- 電子書籍
- 自分でできる子に育つ 最高の言葉かけ …