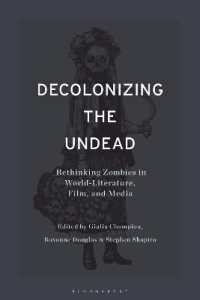内容説明
小学生の15人に1人が「家族の世話」を担い、社会問題として顕在化したヤングケアラー。一般のイメージとは異なり、精神疾患の母親のケアをするケースも多い。こうした事例を含めヤングケアラー経験者たちの語りから実態を読み解く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
78
【子どもとして生きることは実はとても困難な「事業」であり、子どもとは極めて複雑な存在】<「ヤングケアラー」とは、家族にケアを必要とする人がいるために、本来大人がすると想定されているような家事や家族の世話などを行っている18歳未満の子どもや若者を指す言葉。by澁谷智子>。わたしは著者が、<“あいまいな部分が持つ重要性と複雑さ”にこそ本書では焦点に当てていきたい。本書は“労働以外のあいまいな部分を、生活のディテールのつながり合いを発見しながら描く”ことを目的としている>と宣言していることを、高く評価したい。⇒2022/11/05
ゆうき
13
最近よく耳にする『ヤングケアラー』病気の家族の為に介護や家事をしている子供たち。という認識だったがこの本では、いろいろな家庭環境に置かれた子供たちの事が当事者の言葉で書かれていた。全ての子供たちが安全安心の中守られ、学び、遊び、生活出来る当たり前の権利を私たち大人が考えサポートする必要性を感じた。2022/10/18
みき
13
本書では、現象学的方法によって、ヤングケアラー当事者に対するインタビューをもとに、その存在を紐解こうとする。ヤングケアラーを単に虐待された子供と判断するのは、あまりにも単純に物事を捉えすぎていたということがわかった。彼らは置かれた環境の中で、自分自身を位置づけ対応力を身につけて、経験に意味づけをしようとしている人もいる。子供の権利を主張して、ケアする子供とその親を引き離すことを正義とするのは、安易すぎる考えだとわかる。それから、現象学という方法は、研究をするその人の経験さえ、含まれた結果を産むと感じた。2022/08/26
せい
5
大阪・西成区のこどもの里というNPOがつくる地域コミュニティに支えられた子どもたちや、ろう者に関係するNPOに居場所を見出したコーダの方など、何かのコミュニティが支えとなってそれぞれの困難を乗り越えられたヤングケアラーたちのナラティブを紐解いた質的研究の話。平常時から繋がるコミュニティがシームレスな支援やピアサポートを可能にしていくというのはヤングケアラー支援への一つの解答だけど、西成区とか山谷みたいなそういう志のあるNPOが多く集まっている所以外だと難しそうだと思う。2023/01/22
takao
2
ふむ2023/07/02
-

- 電子書籍
- ヒロインなのに、イケメンアイドル♂にな…
-
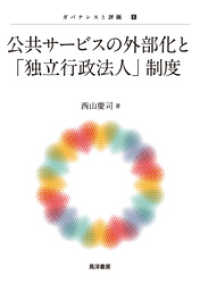
- 電子書籍
- 公共サービスの外部化と「独立行政法人」…