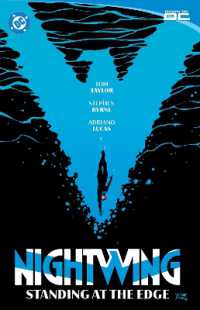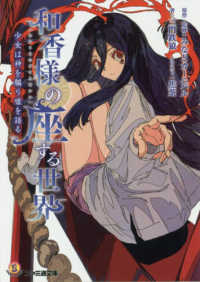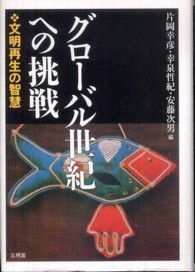内容説明
現在は島根県東部の一地方である「出雲」の名を冠した地名や神社が、列島各地に存在するのはなぜなのか。出雲の謎とは、この国の成り立ちにかかわる問いである。各地に広がる出雲信仰の足跡や伝承、郷土史を丹念に播き、見えづらくなった古来の地域と地域とのつながりを再構成。一つの中心から勢力を拡大していく従来の国家像や近代的な中央集権国家の観念にとらわれない、もうひとつの日本の成り立ちを鮮やかに描き出す。
目次
序章 全国〝出雲〟再発見の旅/1 出雲の中の古志──古代北陸からの移住を刻む地名/北陸の大国/地名で辿る移住・文化史/2 日本の成り立ちに関わる出雲の謎/謎多き国?/神話観の偏り/3 地名や神社で掘り起こす隠れた列島史/海流に沿って伸びる出雲世界/一元的発想の盲点/4 謎の神? ミホススミ──分断された日本海交流圏を結び直す鍵/地域を跨ぐ地域学/輝きを取り戻す女神/第1章 大和神話との矛盾から解く列島の出雲世界/1 記紀神話における出雲の謎/大国主の冒険・国作りを語らない『日本書記』/本文と異なる様々な別伝/2 国を譲らない大国主──出雲神話で迫る史実/特異な風土記──穏やかなスサノオ/大和神話と出雲神話の相いれない齟齬/3 『出雲国風土記』の世界観で見る列島古代史/古代出雲王の末裔/したたかに生き延びた出雲/第2章 出雲を原郷とする人たちを探す鍵──地名や神社で辿る列島移住史/1 出自を刻んだ地名や苗字/移住者のルーツを示す地名/ルーツを屋号や苗字にした人たち/2 人と共に移った神々/氏族移動を物語る古代創建の神社/祭神──風土記の四大神/出雲大神と熊野大神/固有の神の鎮座地を辿る/3 神話・伝承と考古学の成果/神の鎮座や人の移住を語る神話や伝承/考古学的発見──人は使い慣れた道具を移住地に持ち込む/第3章 国引き神話と新羅・高志/1 国引き神話の世界──北ツ海の交流と往来/海から陸を見る地図/「国の余り」は岬、「国引き」は渡来の比喩/列島移住の大動脈──青潮の道/漂流がもたらす文化の伝播や交流/入り海と潟湖/新羅と結ぶ出雲/2 出雲から越前岬へ/そり子と呼ばれた海民たち/血ヶ平の伝説/小舟で海を渡った人たち/出雲人の移住を物語る遺跡/加賀の中の出雲/第4章 能登・越中・越後の出雲を追って/1 外浦航路から邑知潟地溝帯へ──能登における出雲/南北一〇〇㎞で横たわる半島/外浦航路と分岐点の珠洲岬/海を渡りくる寄り神──神像石/気多の由来と連なり/四要素が揃う福野潟の出雲/潟湖を復元してみる/輪島の出雲神社と出雲崎氏/邑知潟地溝帯と平国祭/越の八口の謎を解く/2 越中から佐渡・越後へ──出雲系熊野神社の道/クマノカムロとクシミケヌを祭る神社群/出雲型古墳とウシダケ神社/潟湖畔に鎮座する熊野大神/3 出雲地名が最も多い新潟県/ミホススミの母神・ヌナカワヒメ/出雲崎と佐渡への渡海神話/寄木神社と内陸の出雲田/4 青潮の道が生み出した共通文化/土笛と貝の道/ニライカナイと龍蛇さま/アイの風──万葉集が越の方言と誤解した日本海沿岸の共通語/出雲節──北前船が運んだ船乗り文化/第5章 沿岸から内陸へ──越後から会津・北関東への道/1 東山道・甲州街道説に戸惑う──出雲と諏訪の関係/諏訪大神と千国街道/出雲のそり子舟と諏訪湖のマルタ/2 会津──古代出雲文化の北限/会津の出雲神社群/四隅突出墓の終着地と北陸(系)土器/能登から会津へ──人の移住を物語る遺跡/能登から伝わった会津の気多神社/エミシの領域/出雲とエミシ/3 越後から北関東への道/直江津から北信へ──二つの小出雲/北信の式内伊豆毛神社で合流する二ルート/信濃=千曲川沿いに並ぶミホススミを祭る神社/珠洲焼の出土と重なるミホススミ・ライン/4 北関東に広がる出雲世界/北関東に至る気多神社と熊野神社/北陸系土器からみる北関東入りルート/関東平野の西端に並ぶ出雲イワイ系神社/出雲系横穴墓とされる吉見百穴と山陰系土器の出土/氷川、久伊豆、鷲宮──武蔵東部に広がる出雲系神社群/第6章 瀬戸内と関門海峡を渡って/1 四国北岸の伊予・讃岐と出雲──瀬戸内海の往来/道後温泉と出雲崗神社/山陰特有の甑型土器からみる出雲─伊予間の陸海ルート/尾道と結ぶ出雲街道が生んだ出雲石の伝説/北部沿岸に偏る四国の山陰系土器──瀬戸内海島伝いの道/タキツヒコで直結する出雲と伊予/2 関門海峡をまわり瀬戸内・紀伊水道へ──周防の出雲神社と南紀の出雲崎/周防の出雲神社鎮座の謎を解く/本州最南端の出雲/瀬戸内諸国の屋号が並ぶ大島──四国を臨む日ノ岬/紀伊と出雲の共通性は移住の証か?/3 北部九州に分布する出雲の形跡/筑前国の土師庄出雲/伊都国へ移住した出雲の玉作工人──潤地頭給遺跡/壱岐・新羅の中の出雲/第7章 出雲と大和──畿内への道/1 出雲の東西とヤマト/弥生時代後期~古墳時代初期──出雲西部の繁栄と凋落/古墳時代中期~後期──西部勢力の再興と消失/国譲りの真相/国譲りの時期──三世紀末か、六世紀末か?/出雲西部に偏る征討譚/2 大和国の出雲/纏向の遺跡に残る出雲人の形跡/平城京に出仕する出雲臣たち/出雲国造率いる大訪京団/野見宿禰を祖とする人たち/出雲人形に込めた思い/大和国の出雲氏と出雲庄/初瀬川源流に鎮座する出雲建雄神/旧国名が多い大和国──三宅町の出雲/3 出雲の神や人が頻繁に往来する播磨/もう一つのノミノスクネ伝説/揖保郡周辺に残る出雲神人の伝説/美作道から山陽道へ/家島が物語る瀬戸内海航路/4 出雲臣が集住した山城国の出雲郷/愛宕郡出雲郷とその氏神/隆盛を誇った出雲寺とその凋落/5 若狭湾から山陰道へ──丹波の中の出雲/出雲大神の丹波国開拓伝承と古代山陰道上にある一宮/若狭湾から由良川を遡上する/篠山街道沿いに並ぶ出雲神社──平安京の時代へ/終章 日本海交流の鍵=ミホススミに光を!/1 見えなくなった? ミホススミ/2 美保関の地主神/国引き神話と結びつくミホススミの誕生/ミホススミからミホツヒメへ/えびす様の総本宮/千家俊信『出雲国式社考』の考察/地主社への思い/3 珠洲岬に鎮座する須須の神/奥宮の主祭神/航海の安全を見守る海神/4 出雲・能登以外でのミホススミの祭り/越前・越中のミホススミと鎌倉期の木像/河川灌漑・稲作豊穣の神として祭られる信濃のミホススミ/父娘神の一対で守る灌漑用水/5 信濃・越後でみられる諏訪神との同一神説/ミホススミはタケミナカタの幼名!?/最古の史書から偽書へ──激変した『先代旧事本紀』の評価/越後・信濃で隆盛した諏訪信仰──出雲との温度差/知名度・評価が高まる『出雲国風土記』と同一神説の発生/出雲・高志・信濃の縁を健全に結び直すために/6 地域を結んで浮かび上がるミホススミ像/神霊が宿る岬の女神/美保と須須に坐す女神/地形や生業の類似──姉妹都市となった美保関町と珠洲市/出雲大神の国作りを手伝う長女神/プロジェクトで可視化したミホススミ/おわりに/越境する地域学のススメ/別の鏡で見る自画像/あとがき/コラム1 コトシロヌシとミホツヒメ/コラム2 ミホススミのイメージ像とプロフィール
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
takao
Akiro OUED
-
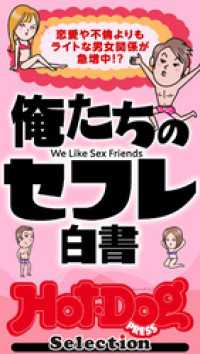
- 電子書籍
- ホットドッグプレスセレクション 俺たち…