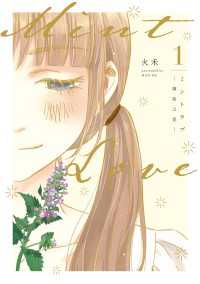内容説明
Rのパッケージを利用した高性能なフリーソフトJASPを利用し,統計解析の要である多変量解析について学ぶ。データ解析を必要とする全ての人が活用できるように、分析方法・結果の解釈・報告例を丁寧に記述した。
目次
1.多変量解析を俯瞰する
1.1 多変量解析とは
1.1.1 データの種類
1.1.2 代表値
1.1.3 散布度
1.1.4 共変動
1.2 多変量解析のロードマップ
1.2.1 複数のデータを分類・要約する手法
1.2.2 複数のデータ間の因果関係を検討する手法
補足:p値と効果量について
2.JASPでデータハンドリングする
2.1 多変量データの特徴
2.2 データハンドリング
2.2.1 データの読み込み
2.2.2 データの種類の変更
2.2.3 データの作成
2.2.4 欠損値の処理
2.2.5 反転項目の処理
2.2.6 条件を満たすデータの抽出
章末問題
3.尺度を開発する
3.1 因子分析とは
3.1.1 因子分析の構造
3.1.2 探索的因子分析と確認的因子分析
3.1.3 探索的因子分析の手順
3.2 探索的因子分析の実行
3.2.1 探索的因子分析の実行
3.2.2 結果の書き方
章末問題
4.既存の尺度・開発した尺度を確認する
4.1 確認的因子分析とは
4.1.1 モデルの適合度指標
4.1.2 因子負荷量や因子間相関の推定法
4.2 確認的因子分析の実行
4.2.1 確認的因子分析の実行
4.2.2 結果の書き方
章末問題
5.テストや尺度の信頼性係数を求める
5.1 妥当性と信頼性
5.1.1 伝統的な妥当性の捉え方
5.1.2 Messickによる妥当性の捉え方
5.2 信頼性係数とは
5.2.1 再検査法
5.2.2 平行検査法
5.2.3 内的一貫性
5.3 信頼性係数の算出
5.3.1 メニューの追加
5.3.2 信頼性係数の算出
5.3.3 結果の書き方
章末問題
6.変数を縮約する
6.1 主成分分析とは
6.1.1 主成分の決定法
6.1.2 主成分数の決定
6.1.3 主成分分析の推定法と回転法
6.1.4 主成分負荷量と主成分寄与,主成分得点
6.1.5 主成分分析の解釈
6.2 主成分分析の実行
6.2.1 主成分分析の実行
6.2.2 結果の書き方
章末問題
7.データを分類する
7.1 クラスター分析とは
7.1.1 階層的クラスター分析
7.1.2 非階層的クラスター分析
7.1.3 クラスター分析の注意点
7.2 階層的クラスター分析の実行
7.2.1 メニューの追加
7.2.2 階層的クラスター分析の実行
7.2.3 得られたクラスターの特徴の検討
7.2.4 結果の書き方
7.3 非階層的クラスター分析の実行
7.3.1 非階層的クラスター分析の実行とクラスターの特徴の検討
7.3.2 結果の書き方
章末問題
8.あるデータの影響を取り除いて平均値を比較する
8.1 分散分析とは
8.2 共分散分析とは
8.3 共分散分析の実行
8.3.1 前提条件の確認
8.3.2 共分散分析の実行
8.3.3 結果の書き方
補足:共分散分析をしないと…
章末問題
9.データを説明・予測する:階層的重回帰分析
9.1 回帰分析とは
9.1.1 回帰分析の方法
9.1.2 回帰分析の結果
9.1.3 回帰分析の注意点
9.2 階層的重回帰分析とは
9.2.1 交互作用の検討
9.2.2 単純傾斜分析
9.3 階層的回帰分析の実行
9.3.1 変数の中心化
9.3.2 階層的回帰分析の実行
9.3.3 単純傾斜分析の実行
9.3.4 結果の書き方
章末問題
10.2値データを予測・説明する
10.1 一般化線形モデルとは
10.1.1 一般化線形モデル
10.1.2 確率分布
10.1.3 リンク関数
10.2 ロジスティック回帰分析とは
10.2.1 ロジスティック回帰分析における切片と回帰係数
10.2.2 オッズ・オッズ比による回帰係数の解釈
10.2.3 ロジスティック回帰分析の評価
10.2.4 ロジスティック回帰分析の注意点
10.3 ロジスティック回帰分析の実行
10.3.1 ロジスティック回帰分析の実行
10.3.2 結果の書き方
章末問題
11.マルチレベルデータを分析する
11.1 マルチレベル分析とは
11.1.1 ランダム切片モデルとランダム傾きモデル
11.1.2 ICCとDEFF
11.1.3 固定効果と変量効果
11.1.4 二つの中心化
11.1.5 マルチレベル分析の注意点
11.2 マルチレベル分析の実行
11.2.1 ICCとDEFFの算出
11.2.2 中心化
11.2.3 マルチレベル分析の実行
11.2.4 モデルの比較
11.2.5 結果の書き方
章末問題
12.質的変数の連関を検討する
12.1 対数線形モデルとは
12.1.1 二つの質的変数における対数線形モデル
12.1.2 三つの質的変数における対数線形モデル
12.1.3 モデルの選択
12.1.4 対数線形モデルの注意点
12.2 対数線形モデルの実行
12.2.1 対数線形モデルの実行
12.2.2 結果の書き方
章末問題
13.変数間の複雑な関連を検討する
13.1 構造方程式モデリングとは
13.1.1 パス図による表現
13.1.2 方程式による表現
13.1.3 変数の区別
13.1.4 構造方程式モデリングの手順
13.1.5 モデルの適合度指標
13.1.6 モデルの修正
13.1.7 構造方程式モデリングの注意点
13.2 構造方程式モデリングの実行
13.2.1 モデルの記述
13.2.2 構造方程式モデリングの実行
13.2.3 結果の書き方
章末問題
14.媒介する変数の影響を検討する
14.1 媒介分析とは
14.1.1 デルタ法
14.1.2 ブートストラップ法
14.2 媒介分析の実行
14.2.1 媒介分析のメニューの追加
14.2.2 媒介分析の実行
14.2.3 結果の書き方
章末問題
引用・参考文献
索引